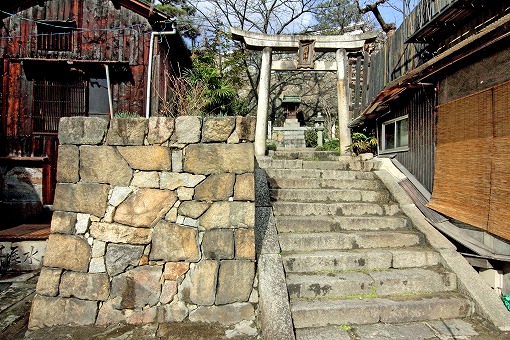1333年(元弘3年)、新田義貞(にったよしさだ)が鎌倉攻めをして北条氏を滅ぼしたとき、神社に戦勝を祈願し、成就の後に黄金(こがね)作りの太刀と黄金を寄進したので、それで社殿を再興したと伝えられます。
その後もたびたび修理や再建が行われました。現在の社殿のうち本殿は、江戸時代の1817年(文化14年)に、腰越全町の人々が協力して建てたものですが、改修されています。また拝殿は、1929年(昭和4年)に建てられたもので、これも改修されています。
1868年(明治元年)の神仏分離で小動神社と名を改めました。
また、1909年(明治42年)は村内にあった諏訪社がここに移されたので、建御名方神(たてみなかたのかみ)もいっしょにまつっています。
カテゴリーアーカイブ: からだの散歩
尾道 伽藍配置で最南端部に造営される「熊野神社」
鎌倉 捨身護法・法華色読の霊地「収玄寺」
福山 鞆 一直線に結ばれた寺町にある「慈徳院」
尾道 江戸時代から続く花火大会「住吉神社」
江の島 たびたび裏山が崖崩れ「延命寺」
鎌倉 この世の花ではない紫陽花「明月院」
尾道 太宰府に左遷さる道真が寄った「御袖天満宮」
厚木 カッパが雨乞いをした「白山神社」
白山神社は、飯山観音背後の白山(標高284m)の山頂付近の尾根道がある。むかしの道は、平野の道は雑草で視界がわるく、手入れも大変だったので、大きな街道を除き、尾根に道をつくることが多かったのでしょう。崩れても手入れが簡単で、視界が得られやすく、道に迷うことも少ないため、尾根を歩くようになったのでしょう。
社殿の前には、池(白山池)があって、古くから雨乞いの霊地とされてきた。
飯山観音(長谷寺)を開いたとされる行基は、この山を登り、霊水が湧き出している池を発見し、加賀国白山妙理大権現を勧請したと伝えられている。
そして、クスノキで彫られた十一面観音が祀られたという。この十一面観音が現在の飯山観音(長谷寺)の本尊といわれている。
鎌倉 足利尊氏が蟄居していた「浄光明寺」
尾道 2020年3月に閉館された「文学記念室 」
福山 鞆 十六羅漢像が安置されている「正法寺」
創建から400年が経った現在においては、枯山水の中に数々のお地蔵様が佇み、境内のお堂には鞆町の多くの信者から寄進いただいた十六羅漢像、そして堂内鬼門には毘沙門天を安置し、鞆の町において心の癒やし場として親しまれております。
釈迦からこの世にとどまり仏法を護るように命じられた十六羅漢
1.賓度羅跋羅堕闇尊者(びんどらばらだじゃそんじゃ)
2.迦諾迦伐蹉尊者(かなかばっさそんじゃ)
3.迦諾迦跋産堕閣尊者(かなかばりだじゃそんじゃ)
4.蘇頻陀尊者(そひんだそんじゃ)
5.諾矩羅尊者(なくらそんじゃ)
6.跋陀羅尊者(ばだらそんじゃ)
7.迦哩迦尊者(かりかそんじゃ)
8.伐闍羅弗多羅尊者(ばしゃらほったらそんじゃ)
9.戎博迦尊者(じゅはくかそんじゃ)
10.半諾迦尊者(はんたかそんじゃ)
11.羅怡羅尊者(らごらそんじゃ)
12.那伽犀那尊者(なかさいなそんじゃ)
13.因掲陀尊者(いんかだそんじゃ)
14.伐那婆斯尊者(ばなばしそんじゃ)
15.阿氏多尊者(あしたそんじゃ)
16.注荼半託迦尊者(ちゅうだはんたかそんじゃ)
羅漢とは、悟りを開いた修行者という意味です。