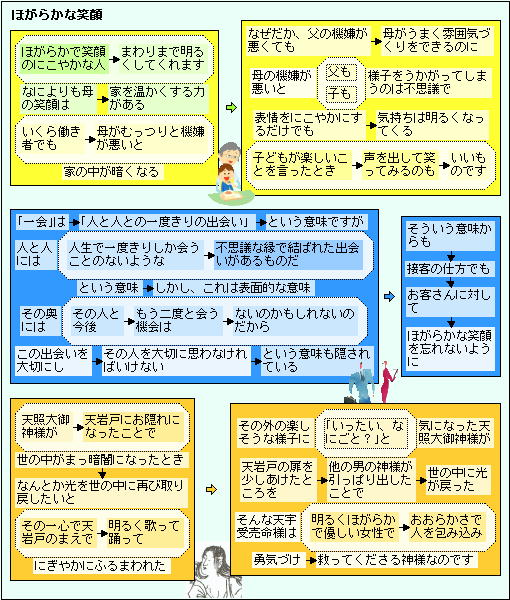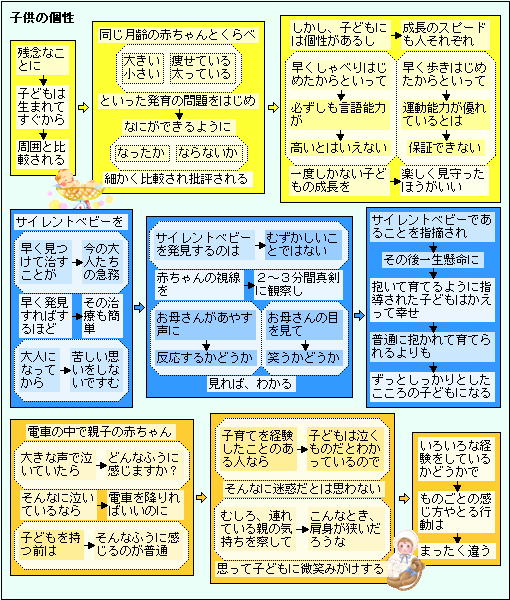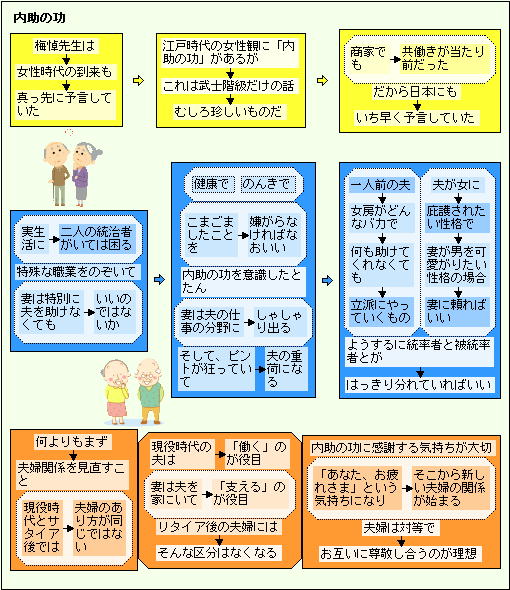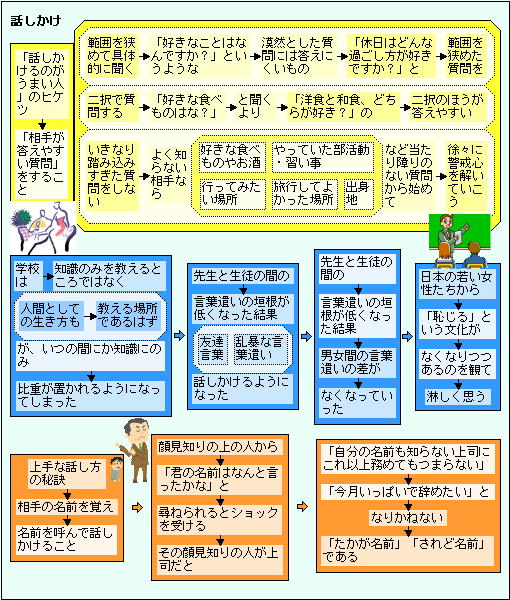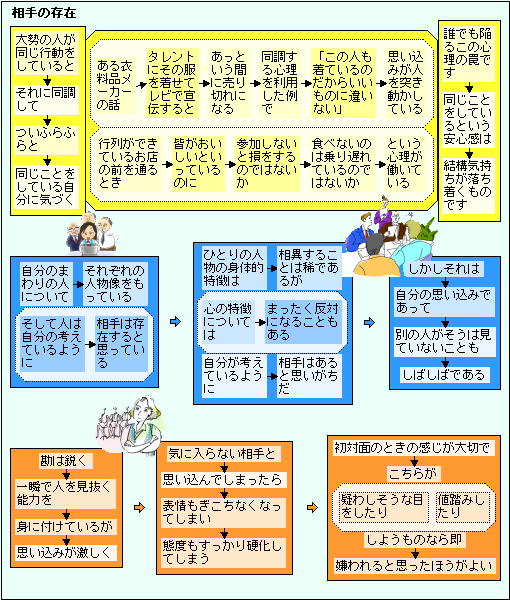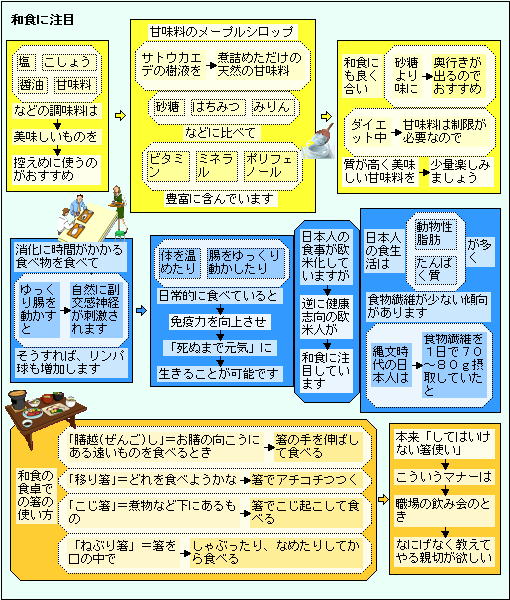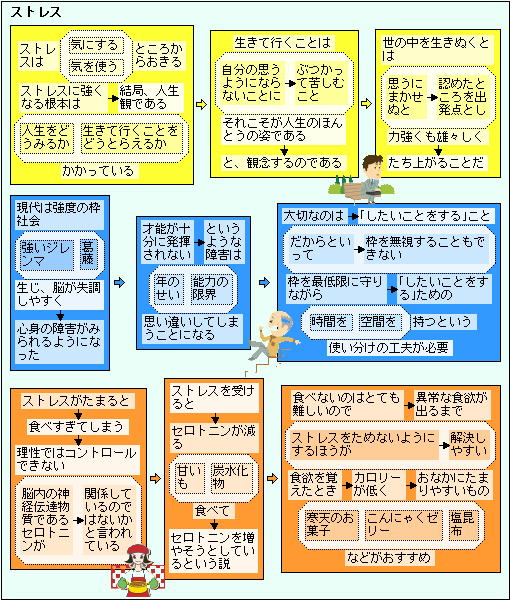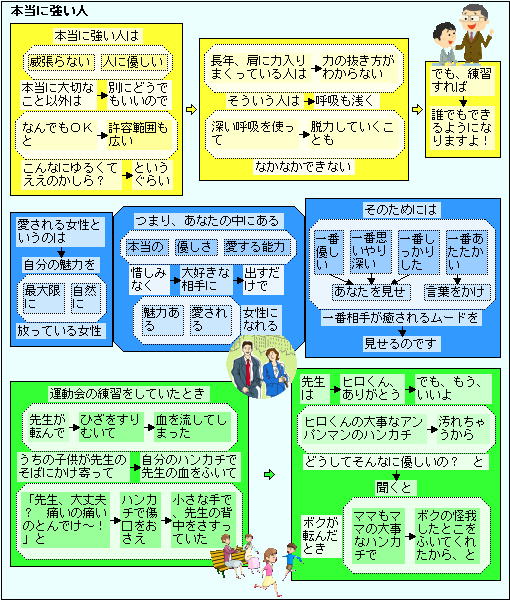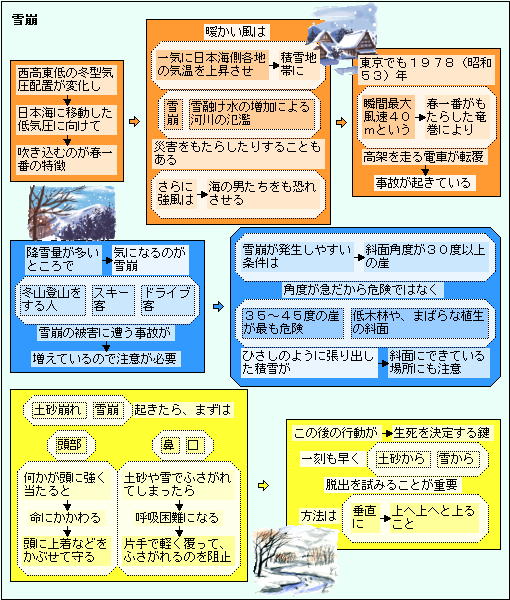持光寺の石の門(延命門)
「ええ門は福善寺、かたい門は持光寺」…童歌までに唄われた同寺の門はそのものズバリ、主体だけ17個からなる花崗岩を組みあわせトンネル状に築きあげた石の門。全巾が5m、奥行き3.5m、高さ3.5mで、通路が巾3m、高さ2.8m。これだけの石を据え微塵の狂いを生じてないあたり、基礎に相当の配慮がはらわれているのだろう。約三百年前に建てられたものであろうが、当時の築構技術の粋をあつめた“石の町”ならでの逸品。
付近の古老のはなしでは、門の上に柱をたてるためのものであろう穴が数個あったと聞かされ、梯子を借りて屋根まで登つたが、薄くセメントがはられ穴の確認はできなかつたが、おそろく天寧寺などで見られるように鐘楼門にする計画であったのが石の基礎だけ出来あがったところで挫折したのであろう。
(「郷土の石ぶみ」 明治31年5月10日創刊 山陽日日新聞社 より)