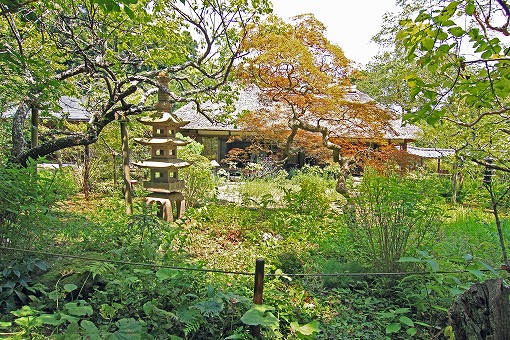境内には清明石なるものがある。昔は十王堂橋を渡った道路の真ん中にあったらしい。この石をわざと汚したり、踏みつけたりすると祟りがあるという。しかし、この石を知らずに踏むと足が丈夫になり、足を痛めた人は石を清水で洗い、塩や線香をあげて拝むと治るとも言われたという。道路工事のため八雲神社に移された。清明とは平安時代の陰陽師安倍清明(あべのせいめい)のことであろうが、鎌倉には火事と清明にまつわる話が残されている。治承4年(1180)10月に鎌倉に入部した頼朝は、当初山ノ内にあった知家事兼道なる人物の館を移築してそこに住んだという。この家は「晴明朝臣鎮宅の符」があったため200年間火災にあっていないという由来があったという。山ノ内には安倍清明の屋敷があったという言い伝えがあるが、明確ではない。
カテゴリーアーカイブ: からだの散歩
尾道 もとは海徳寺の鎮守だった 「勇徳稲荷神社」
軒が低く打ち水が涼気を誘う後地小路をくぐりぬけるとまねくが如く道路にセリだした松の木の根元にギョッとするほど鮮やかな朱塗の鳥居が待ち受ける。もともと正一位 勇徳稲荷神社は海徳寺の鎮守であったが、大正十五年に同寺が火災にあい、このため寺は、東久保町の山手に引っ越したが、神社だけは独立し、そのころの名ごりをとどめ「抱二天」の仏様がまつられている。
鎮座はこれまたいつのころかわからないが鏡台に文久二年(一八六二)と書きこんであるところからこれよりさかのばるものとみられ、間口三間ほどの拝殿はそう古くはないが玄関は昭和年代に入り、近くの御嶽教社をとりこわし移し、また鳥居も元市民病院横にあった稲荷様のものといわれる。
もともとは海徳寺の鎮守であったが、1926年海徳寺が火災にあい、山手に引っ越した。そのため、神社は独立しました。
座間 不動池には豊富な湧水が「心岩寺」
鎌倉 寺地工事中、地中から石櫃が現れた「円覚寺仏殿」
福山 航海の安全を祈る「陸奥稲荷神社」
尾道 大草鞋サイズの足の大男がいる?「西国寺山門」
鎌倉 時宗宗祖・一遍は「ものを捨てよ」と「光触寺」
尾道 1957年死者・行方不明113名沈没事故「瀬戸田港」
1957年4月12日「第五北川丸沈没事故」がありました。午後0時30分に瀬戸田港から尾道港への帰途についた芸備商船の定期客船・第5北川丸が出航。この客船は、定員が84名であったにもかかわらず、235名(うち子供12名)が乗船。旅客定員の3倍超の乗客と乗員4名を乗せていました。しかも同船は建造から33年(1924年建造)経過した老朽木造船でした。乗員5名のうちひとりを別の用事のために下船させたため、船長自らが切符整理を行い、舵を当時16歳の甲板員見習(事故により死亡)に任せていました。
生口島の瀬戸田港から尾道港に向け出航しておよそ10分後、佐木島西方にある寅丸礁(事故後、灯台が設置された)と呼ばれている暗礁に座礁・転覆し、あっというまに沈没してしまいました。付近を航行していた運搬船や漁船がただちに救助に当たったのですが、船内に閉じ込められるなどして死者・行方不明113名、負傷者49名を出す惨事が起きてしまいました。
厚木 樹齢約600年の御神木イチョウ「荻野神社」
鎌倉 鎌倉にある唯一の尼寺「英勝寺」
尾道 お茶子娘供養のかんざし燈籠「八阪神社」
「かんざし灯籠」の伝説
……ある日、だんなが息子を呼んで言うた。
「おまえ、お茶子ふぜいと付き合うとるそうじゃが、立場を考えにゃいけん。うちは浜問屋じゃけえのう」
「浜問屋とお茶子がどうして結婚してはいけんの」そんな親と子のやりとりが何日も続いた。……息子がつれてきた娘を父親はじろじろと見まわした。
べっぴんさんじゃし、言葉づかいもていねいじゃし、気立てもよさそうじゃ。……「あんたべっぴんさんじゃし、言うことはないけどのう、今時の娘がかんざし一つ差しとらん。かんざし一つ差しとらんような者を、うちの嫁にするわけにはいかんのじゃ。すまんがうちの息子との結婚はあきらめてくれ」……そう言われて娘は悲しかった。
この日のために親が無理して買うてくれた着物と履物。じゃが、かんざしまでは手が届かんかった。娘は親の気持ちを考えると、ただただ、せつなかった。 両親の顔が浮かんでは消える。
気持ちのやさしい娘は心の中で両親にわびながら、その夜、明神さんの近くの井戸に身を投げて死んだんじゃ。
それから間もなく、雨の日に女の幽霊が出るという噂がたつようになった。