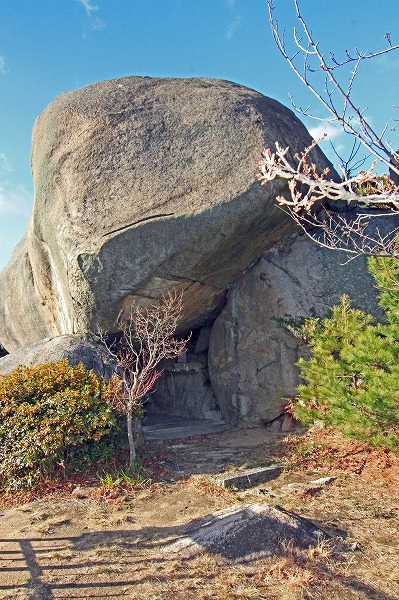“ 幕末の風雲急を告げる1867年の末、芸州藩は片岡大記を大隊長とする一個大隊を派兵し、この寺を本陣として尾道を鎮め東の福山藩に備えた。この寺は尾道地方に数少ない幕末維新の史跡である。
慶応三年(1867)十五代将軍徳川慶喜は内外の情勢を察し大政奉還を断行。このとき芸州藩は尾道の重要性を認め、片岡大記を隊長として一箇大隊の兵を海路尾道に送り、また意気たからに長州藩の鉄砲隊もくりこみ寺院に分宿、目と鼻の先の福山に徳川の譜代衆阿部氏と対峙した。尾道には官・幕双方の密使やスパイが入り乱れ一触即発の危機をはらんでいた。そのような緊迫状態のなかで芸州藩の支隊が西国寺にも駐屯した。また、血気はやる地元民などで結成された隊士らが、乱暴をはたらき刑に問われたものもある。
(尾道は、大半が芸州藩、東の外れ側が福山藩(井伊直弼の一つ前の老中首座が阿部正弘で、福山藩の藩主。) ”