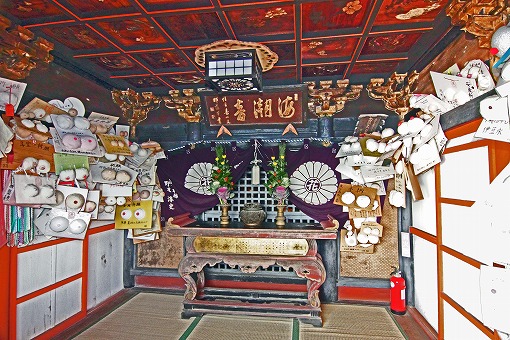足利義昭が身を寄せていた(後ろ山の奥、熊野町の)常国寺の末寺であったが絶えて、慶長年間(1596~1614年)1600年頃、福島正則(芸備藩主)によって、この顕政寺などの寺々をほぼ一直線に結ぶ寺町(町割り)が形成されました。
正善院日実は顕政寺を再建し、日蓮宗に改め二代・日運は、本堂と庫裡を拡張する事績を遺し、四代目の日富は、延宝年中(1673~1680年)に、奉行・藤井六郎右衛門に願い出て門前の境内を拡め、今日の基礎を築いた。と伝えられています。
自分を見つめ直すことができる癒しのお寺として、「観心行」を行っています。観心行は、日蓮宗の修行ですけど、ここではオリジナルが行われています。
特に宣伝はしていないようです。
観心行は、文字通り「心を観る行」。日常の中で自分が行なった良いことや悪いことを思い出し、それらを見つめ直し、手放していく修行。ここでは10分程度のシンプルなものでになっています。
カテゴリーアーカイブ: 福山 鞆
福山 「鞆の大仏」とも阿彌陀如来坐像も「阿弥陀寺」
1748(延享5)年に、宇和島藩の接待によって朝鮮通信使の宿が「阿弥陀寺」に移ったとき、眺めが悪いためか通信使一行は抗議して船に帰ったといいます。
通常、朝鮮通信使のための迎賓館として使用されていたのは、福禅寺の客殿で1711(正徳元)年、この客殿からの眺望を「日東第一形勝(対馬から江戸までの間で一番美しい景勝地という意味)」と称賛、従事官の李邦彦はその書を残しています。
朝鮮通信使とは、李氏朝鮮が1404年から日本に派遣した外交使節で、豊臣秀吉による朝鮮侵攻のあと途絶えていたが、1607年から再開されました。
江戸時代には、1811年まで12回、朝鮮通信使が日本を訪れている。その中心のメンバーは外交担当の役人や武官だが、さまざまな随行員も含めると、毎回なんと約400人もいました。
福山 鞆 「日東第一形勝」と賞賛「福善寺対潮楼」
福山 鞆 「こがらっさん」の愛称の「小烏神社」
福山 龍馬評価が変わってきた「いろは丸展示館」
1988~89年に行われた潜水調査の模様や、その時に引き揚げられた物や調査の様子がわかる写真、そのほかの龍馬に関わる資料などが展示されています。
いろは丸事件ば、慶応3年(1867)4月、龍馬は海援隊を組織し伊予大洲藩から借げ受けた西洋式の蒸気船「いろは丸」に乗って長崎から大坂に物資(鉄砲)を運ぶ途中、岡山県六島沖(現在の同県笠岡市)で、紀州藩の蒸気船「明光丸」に横から衝突されたのです。明光丸は鞆港へ向けて、いろは丸を曳航しようとしましたが、浸水のため宇治府沖で沈没してしまいました。
このため両者は鞆の浦にとどまりの損害賠償について昼ゆ夜交渉を繰り返しましたが決裂し、舞台を長崎に移して再交渉を行いました。龍馬は、交渉の部隊を長崎に移すことで時間稼ぎをし、その時間を利用し、様々な工作を行ったようです。最終的に、龍馬側が賠償金を受け取る、ことでようやく決着しました。
この事件は、坂本龍馬が暗殺される半年前のことです。

福山 鞆 水軍の拠点だった大可島「圓福寺」

当寺院の建つ場所は大可島といい、鞆港の入り口に浮かぶ島だった。頂きには海城が築かれており、南北朝時代には北朝・足利幕府軍と南朝・後醍醐天皇軍との合戦の舞台となりました。
戦国時代には村上水軍の一族がこの海城を拠点にして、海上交通の要所・鞆の浦一帯の海上権を握っていました。
福島正則が鞆城を築いた慶長年間(1600年頃)に、埋め立てによって大可島が陸続きとなりました。城は廃城となり、慶長15年(1610年)頃に大可島城(たいがしましろ)の跡地に移転し、建造されたと伝えられています。江戸時代は真言宗明王院の末寺となっていました。朝鮮通信使が来日した際には上官が宿泊しました。
いろは丸沈没事件の談判の際、紀州藩の宿舎に使用されました。
福山 鞆 鬼子母尊講中お題目碑がある「妙蓮寺」
福山 鞆 石山合戦に参加した「明圓寺」
“ 承久年間、沼隈郡山田村に建立された小坊が元とされています。当初は天台宗を奉じていましたが、1238(歴仁元)年、山南村光照寺の明光上人の導きで真宗に改宗しました。
鞆の浦への移転は文明年間、山田村の領主に日蓮宗への改宗を迫られ、これを拒否した直後のことです。戦国時代末期にあった織田信長と本願寺の戦い(石山合戦)では、住職の長存が備後門徒を集め、「進者往生極楽、退者無間地獄」の旗を掲げて奮戦し、その後は東本願寺設立にも尽力しました。「松江山明圓寺」の寺号はこれらの功績により、教如上人から授けられたものです。
石山合戦は、浄土真宗本願寺勢力と織田信長との戦いです。浄土真宗本願寺派は、武装もするし、非常に自主性の高く、横並びの感性が非常に高い集団だったそうです。”
福山 鞆 箏曲家宮城道雄の先祖墓がある「南禅坊」
“ 天正年間(1573~1591年)に創建したと伝えられる。
元々、福禅寺下にあったが、江戸中期(正徳年間・1711~1715年頃)に現在地に移転する。 寺院調査の中で、「梵鐘一件記録」が発見され、鐘の供出を巡る経過を詳しく記した史料として貴重である。かって、その鐘があった鐘楼門(山門)は現存する。
なお、境内には、宮城道雄(「春の海」(箏と尺八)の作曲家・箏曲家)の先祖墓がある。 江戸時代を通して、朝鮮通信使の常宿でもあった。
朝鮮通信使とは、李氏朝鮮が1404年から日本に派遣した外交使節で、豊臣秀吉による朝鮮侵攻のあと途絶えていたが、1607年から再開された。
江戸時代には、1811年まで12回、朝鮮通信使が日本を訪れている。その中心のメンバーは外交担当の役人や武官だが、さまざまな随行員も含めると、毎回なんと約400人もいた。”
福山 鞆 新羅へ出兵の淀媛命を祀る「淀媛神社」
この神社の祭神は淀姫命(よどひめのみこと)。三韓征伐を行った神功(じんぐう)皇后の妹君で、はじめは、海神・大綿津見命(おおわたつみのみこと)を祀った沼名前神社(渡守神社)の祭主を務める身でした。しかし、後世、その徳が偲ばれて氏神として奉斎され、鞆湾の入口を守護する守り神となりました。以降、この高台に鎮座し続け、現在に至っています。
神功皇后が三韓征伐のため西国下向の際、鞆の浦の地に寄泊しました。帰路携帯していた「鞆」を奉納し、海神・大綿津見命を祀った際に、妹君の淀媛命を祭主として奉任させました。その神社が沼名前神社(渡守神社)の起源です。
数年後に淀姫命は鞆の浦を去りましたが、後世その特を偲び氏神として奉斎し、鞆の浦湾の入口の丘の上に鎮座する護り神として現在に至ります。
福山 鞆 瀬戸内の要港にある古刹「小松寺」
福山 万葉集にも歌われた「昔の鞆の港」
福山 戦国時代、安国寺恵瓊が再興した「安国寺」
この安国寺の歴史が再発見されたのは1949(昭和24)年。解体修理が行われた安国寺の阿弥陀三尊像の中から古文書が見つかった時である。
安国寺は本来、金宝寺。室町時代に寺社名、歴史が書き換えられたと分かった。
阿弥陀三尊像、法燈国師坐像やこれらを収める釈迦堂など、安国寺は国、県指定文化財を蔵するが、すべて金宝寺時代のものだと判明した。
(「知っとく? ふくやま」 監修 松本卓臣/平井隆夫より)
安国寺の住持を務めていた安国寺 恵瓊(あんこくじ えけい)という人物。
恵瓊は戦国時代から安土桃山時代にかけての人物で、京都の東福寺と更には安芸と鞆の両安国寺の住持を兼務する臨済宗の僧でありながら、毛利氏三代(毛利元就・隆元・輝元)に仕えた武将としても名を馳せました。
更には豊臣秀吉にも重用され大変な実力者となりましたが、関ヶ原の戦い(1600年)で西軍の拡大に暗躍(ひそかに策動)したが敗北。後に捕まり死罪となってしまいました。
それにより安国寺は衰退。東福寺の力が薄れた安国寺が江戸初期に京都妙心寺の末寺となったことから、安国寺と関わりが深かった当寺もそれと同じ道をたどり、東福寺派から妙心寺派へと改まったものと考えられます。
福山 鞆 神功皇后が海路安全を祈る「沼名前神社」
福山 鞆の浦 鞆湾の全景が一望の「医王寺」
医王寺は、平安時代に弘法大師によって開基されたと伝えられるお寺です。
坂道や階段を上った先の後山(うしろやま)の中腹に、鞆の浦で2番目に古いお寺 医王寺があります。このお寺は826(天長3)年に弘法大師空海によって開基されたと伝えられています。その後、火災で焼失していますが、慶長年間に、鞆城代・大崎玄藩により再興されました。
高台にあるため眺めは最高で、鞆湾の全景が一望の下に見渡せます。
医王寺の足下の街道沿いには、江の浦・「焚場」の集落が道沿いに細.長く広がり、その向こ鞆港が大きく弧を描いています。さらに、港の北に広がる鞆の町並みの向こうには、仙酔島が望まれます。
文政9年(1826年)に、鞆に寄港したオランダの医師のシーボルトも、植物観察のために医王寺を訪れており、この景観を楽しんだでしょう。