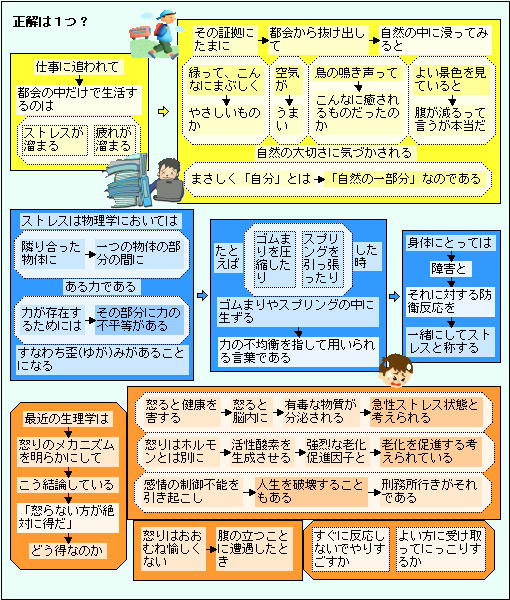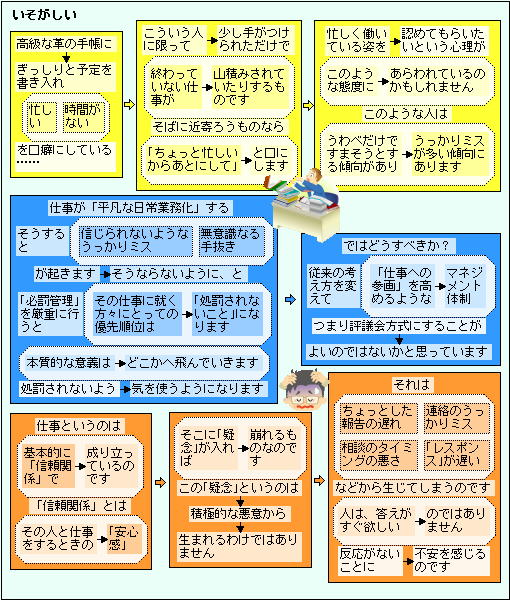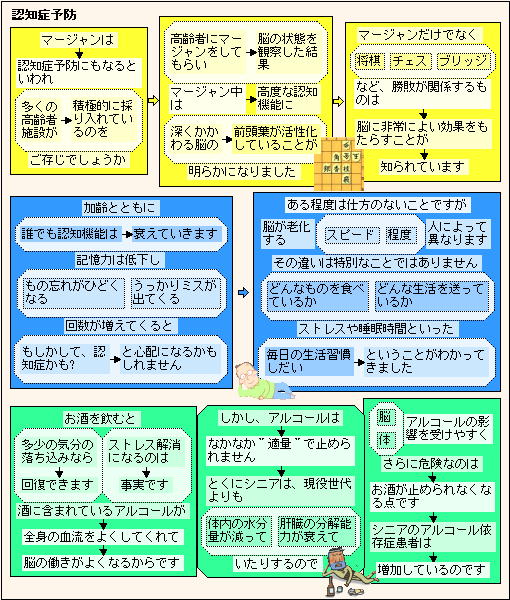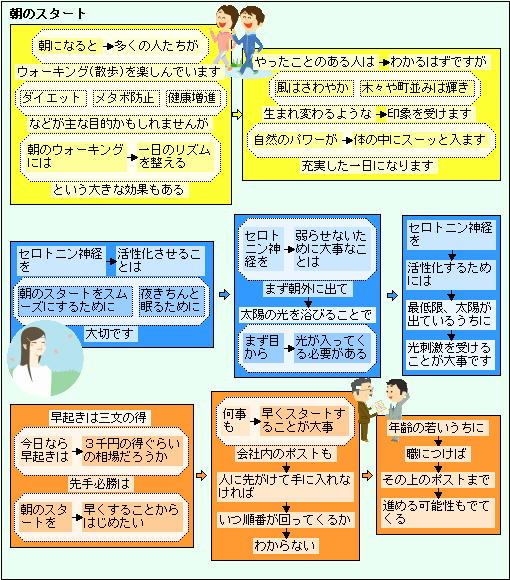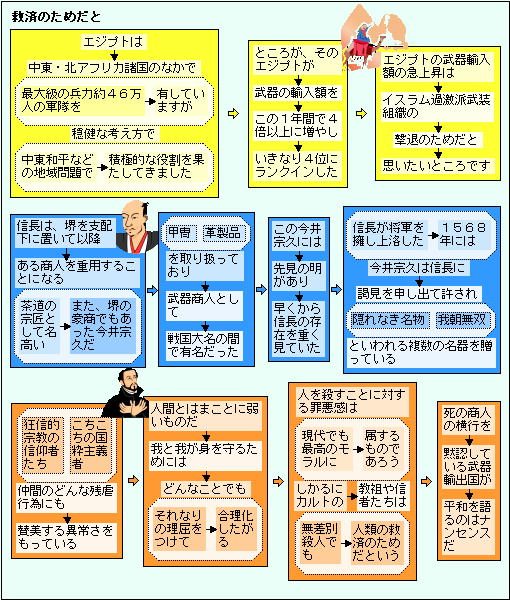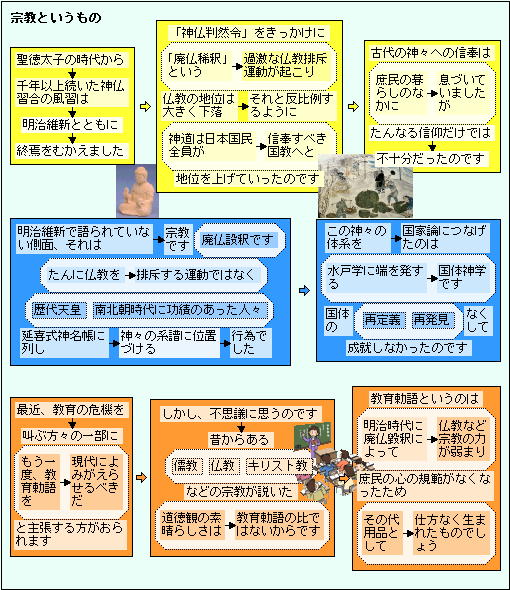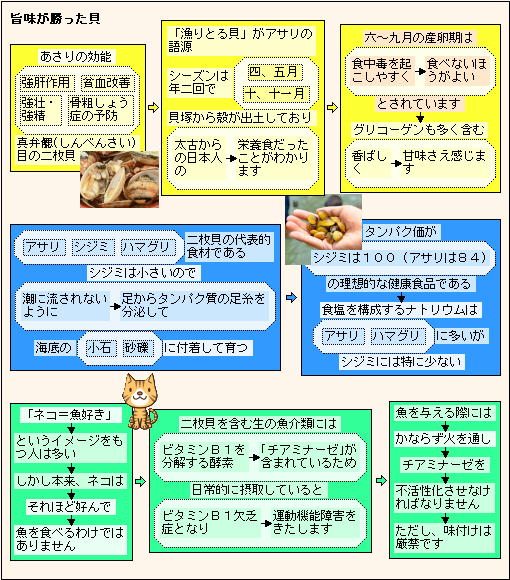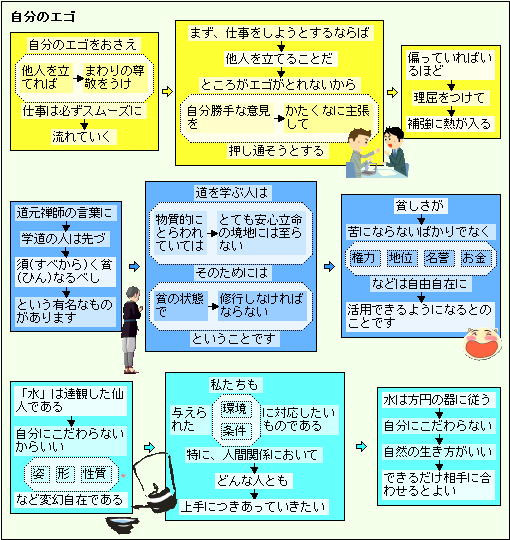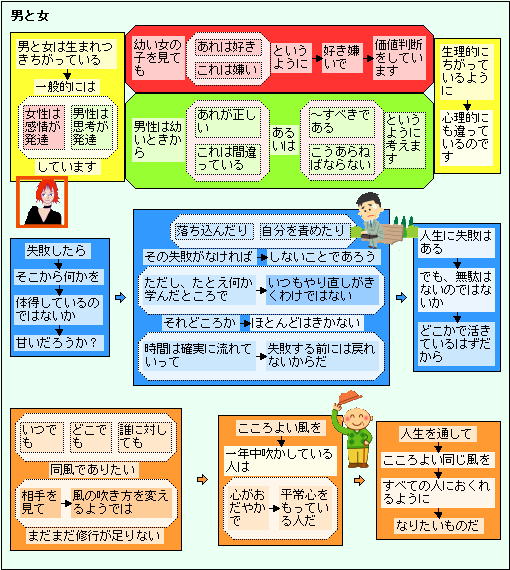“ 日蓮上人の鎌倉草庵の地。
日蓮が世間をあっと言わせた出来事があった。極楽寺の忍性との雨乞い競争で、まづ忍性が祈り始め、七日の内に雨を降らせると公言したが、結果はさんざんで、七日たっても一滴の雨も降らなかった。忍性と数百の供僧たちが更に24日間祈りに祈ったが、ついに雨は降らなかった。日蓮はこれを見て、民をかわいそうに思い、一人で七里ヶ浜の田辺ヶ池の畔で読経したところ、たちどころに雨がしとしと降り出し、異常乾燥も終止符を打ったという。この一件が敵方をより過激にし、激しい迫害を受ける一因になった。
裏山の富士見台からは由比ガ浜海岸を含む市内を一望できる。”