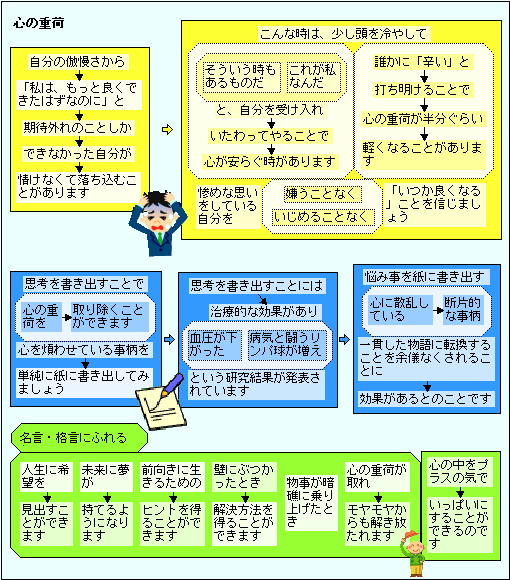むかしの人は「恨み」が、自分にとっても害があることを知っていたのでしょう。草木も眠る丑三つどき(午前二時から二時半ごろ)、寺社に参詣し、呪う相手に見立てた藁(わら)人形を境内の神木に取りつけ、人形の体に五寸釘を打ち込む。そうすると呪われた相手は、釘が打ち込まれた部分を損傷するという。「丑の刻参り」である。この丑の刻参りは、平安時代ごろから始まったようです。こんな時間帯になぜ寺社へ赴くのか。丑の刻参りは人に知られずにこっそり行なわなければならないとされているからです。
カテゴリーアーカイブ: あたまの散歩
早くから天皇は国の祭祀をつかさどる存在!
誰かがわかってくれたら!
「相手」に「意識」を向ける練習!
自分だけしか通用しないモノサシ!
ニコニコ笑っているけれども「怖いぞ」!
情報は自分の全身で目で耳で!
テレビ番組「人間ってナンだ?超AI入門」で、「知識」について、人間の知識を二階建ての建物にたとえ、一階は「感覚」で得た情報、二階は「言葉」で得た情報と位置づけ、この両方の関連付けがうまくいくと、理解が深まっていくとのこと。AIは二階の部分を高度化しており、一階の感覚情報の部分は、犬や猫よりはるかに劣っているため、二階の言葉情報を大量に蓄積することで、一階の部分をカバーしようとしているとのこと。人間も、昨今は一階の感覚部分の情報量が少なくなっており、言葉情報を正確には理解できていないようです。このため、自然がもっている「多様性」を、感覚的に理解していないため、同じような人を仲間にし、異質な人を除外(いじめを)するのでしょうか!