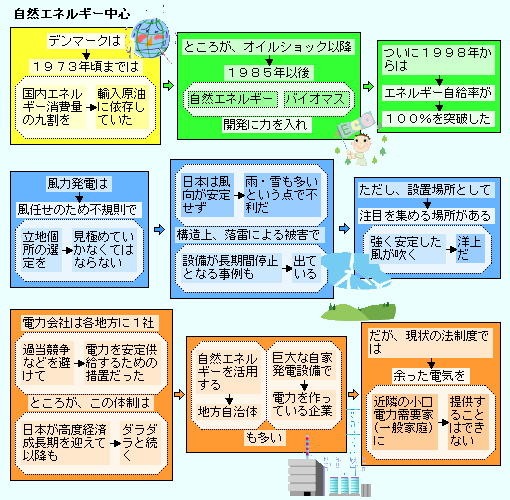
エコが叫ばれています。昭和30年(1955年)頃までの生活スタイルは、今に比べればはるかにエコ生活でした。
そのエコ生活のノウハウを、実体験の人たちから早く教わっておきたいものです。知識人の人たちは、なかなか当時の生活体験が少ないので、難しいものかもしれないですね!
TEL.03-1234-0000
〒163-0000 東京都○○区○○○1-2-3
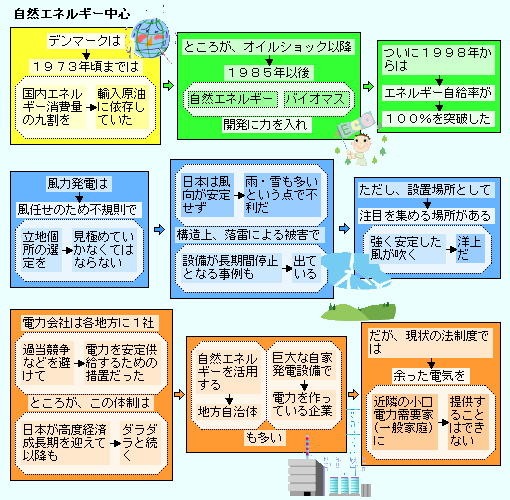
エコが叫ばれています。昭和30年(1955年)頃までの生活スタイルは、今に比べればはるかにエコ生活でした。
そのエコ生活のノウハウを、実体験の人たちから早く教わっておきたいものです。知識人の人たちは、なかなか当時の生活体験が少ないので、難しいものかもしれないですね!
尾道や瀬戸田は、中世から瀬戸内海交易の中継地として発展し、江戸時代においても有数の港町でした。北前船が寄港するようになると、さらなる飛躍をとげています。
尾道では、1689年に薬師堂浜の西側を、1690年にさらに西の荒神堂浜を、1697年に土堂浜を埋め立てています。この埋立は商人たちの手によるもので、増大する船舶の出入りに応じる形となっていました。
この後、さらなる港の活性化に伴い、住吉浜の築造が急務となりました。そこで、広島藩は、直接工事を計画し、1740年尾道町奉行に平山角左衛門を任命。平山角左衛門は、翌年工事に着手し、住吉浜を築造しました。
(神社は昭和の初期までは、こちら側(海側)を向いていたようです。)
開基(創立者)と開山(初代住職)はともに不詳だが、高徳院では法然上人を開祖としている。
当初は、阿弥陀大仏を安置する大仏殿以外には付属する建物はなく、もともとは「大仏殿」が正式名称だった。
1238年に着工した大仏は木造。1247年、大風で倒壊。1252年に現在の青銅で鋳造された。1495年の津波で大仏殿が流され、露天の大仏になってしまった。この年は北条早雲が小田原城を奪取した年であり、鎌倉はすでに大仏殿を再建する経済力はなかったのでしょう。
かってこのあたりは鎌倉の西の果て、そのため、刑場があったり、流人が集まる場であったり、ハンセン病患者の収容施設があった場所。そうした場所を大仏によって「悪書」を「聖化」し、都市鎌倉、そして関東地方を護持させようとした。