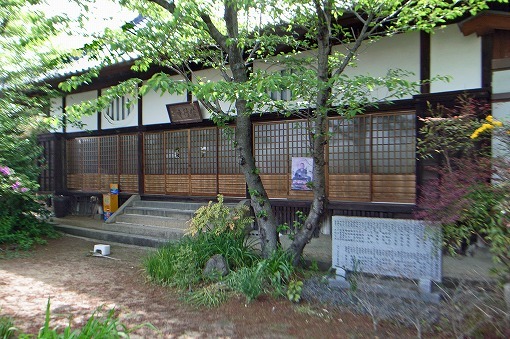幼いとき「聴いて貰っている」その姿を目で見る経験は、その後の社会生活において重要なことなのでしょう。まだ、言葉が話せない赤ちゃん時代に、まわりの人たち(親や兄弟、祖父母など)が、聴く姿勢を見せることが、その後の人づきあいに関わる脳の発達に影響を与えるのでしょう。人類が言葉を手に入れたのは数千年前、それまでは、表情筋の進化で得た多彩な表情と、白目がある人間の目の動き、そして、叫び声に類するもので伝えていたのでしょう。人類の歴史から見れば、言葉はつい最近のこと。それまでは、相手が自分を理解しようとしている表情や、視線、姿勢が重要な役割をしていたのでしょう!