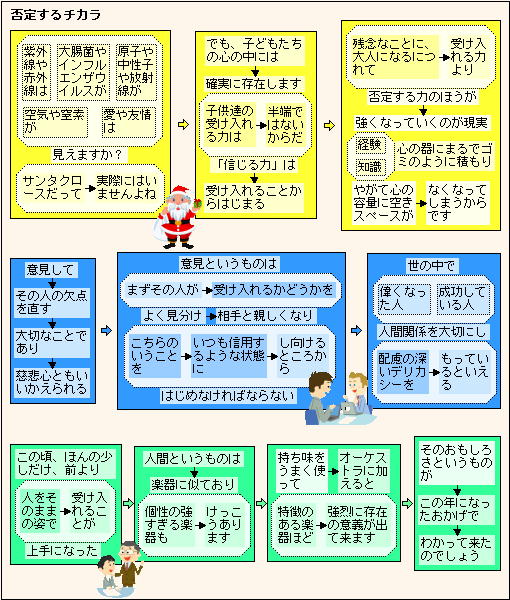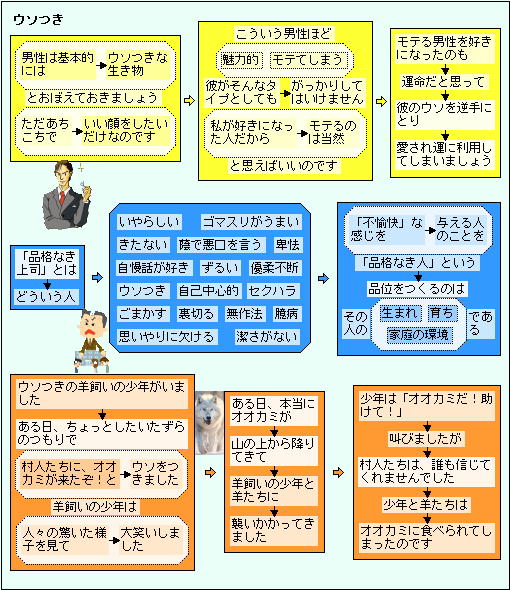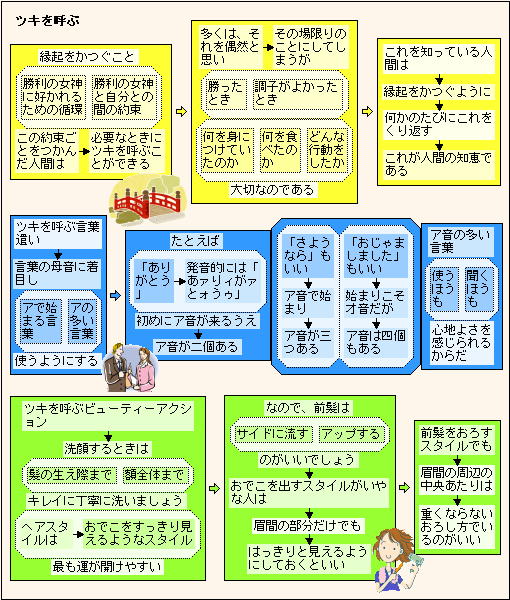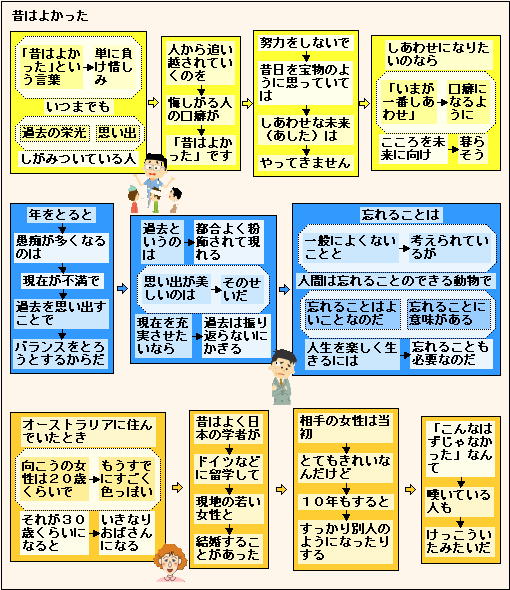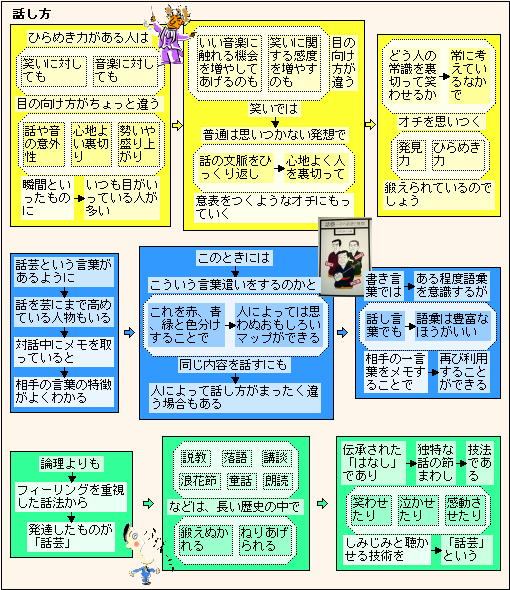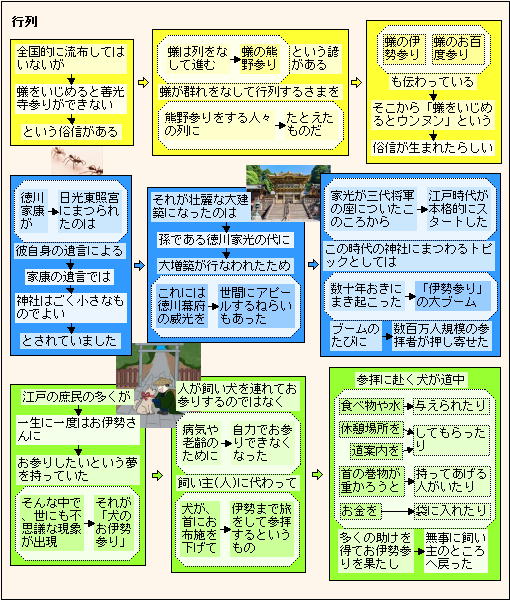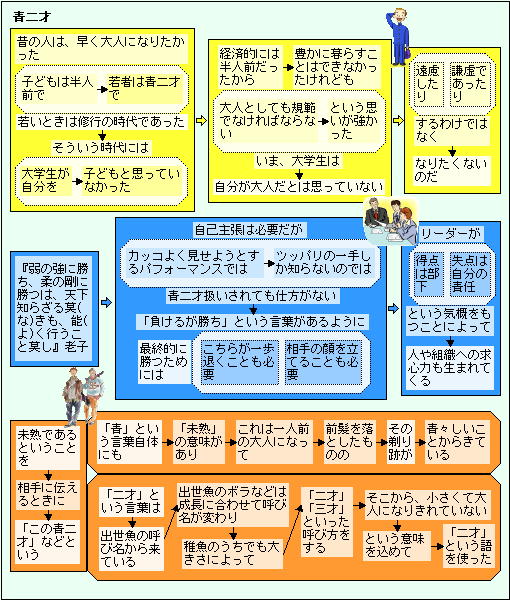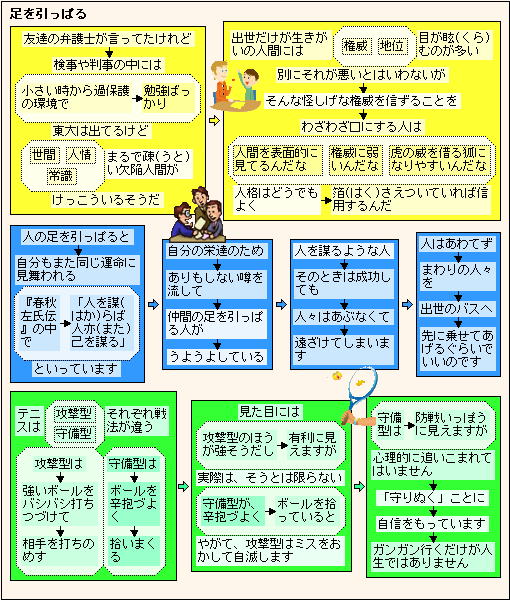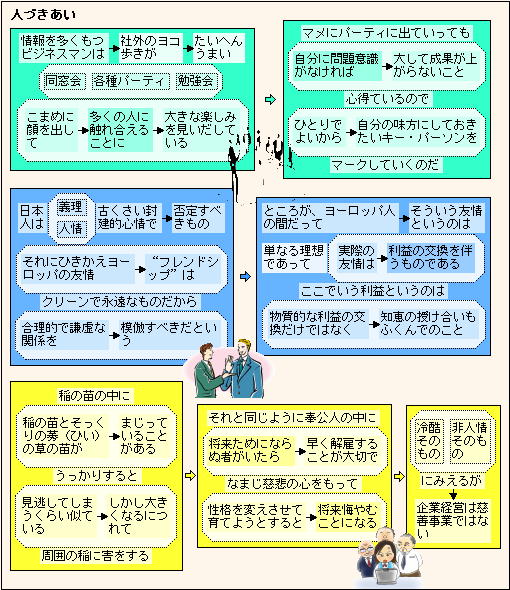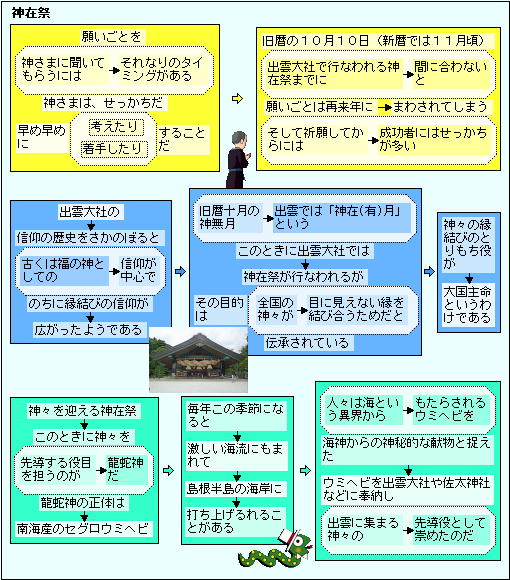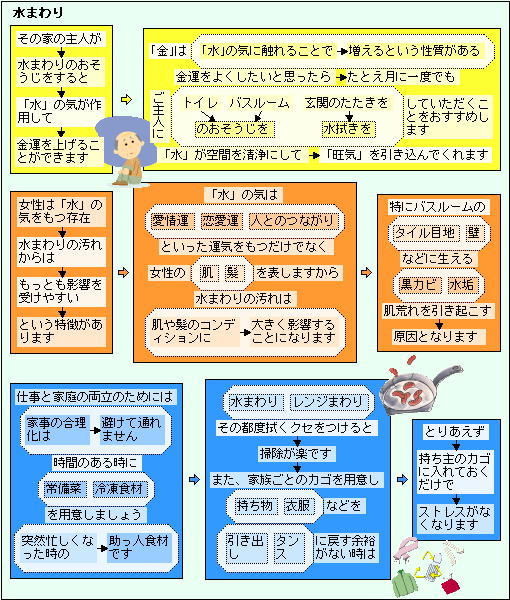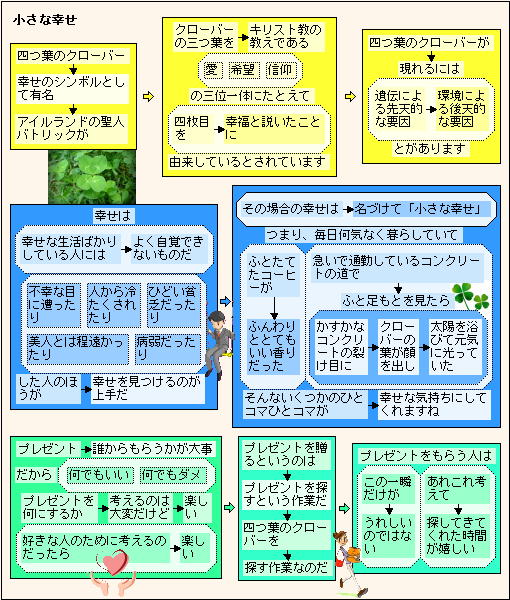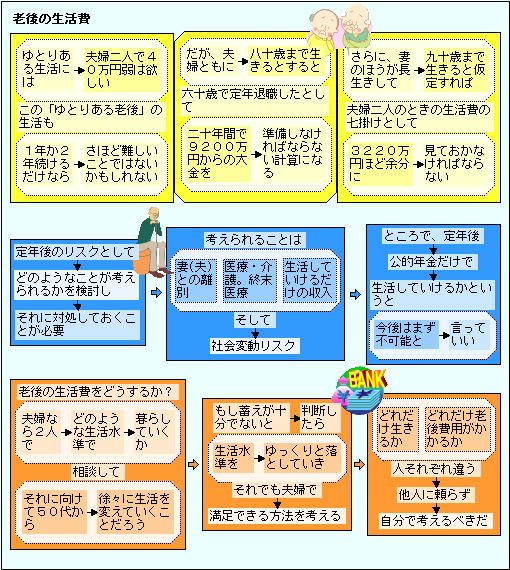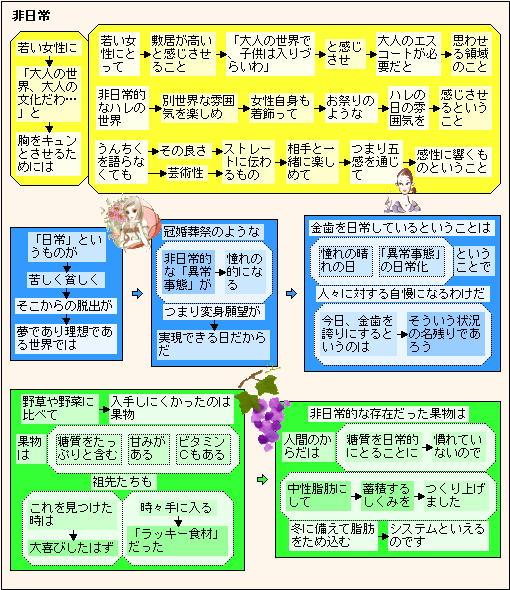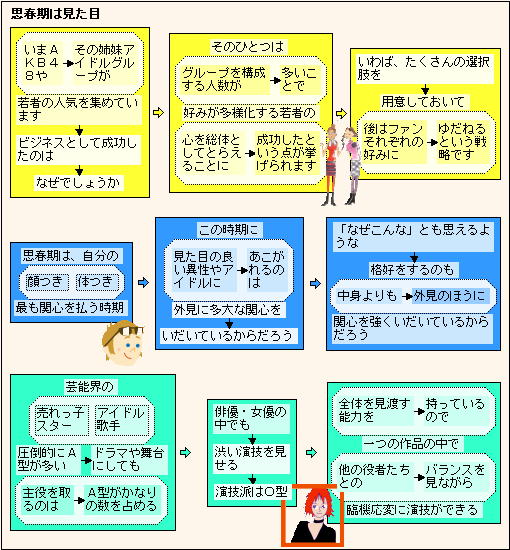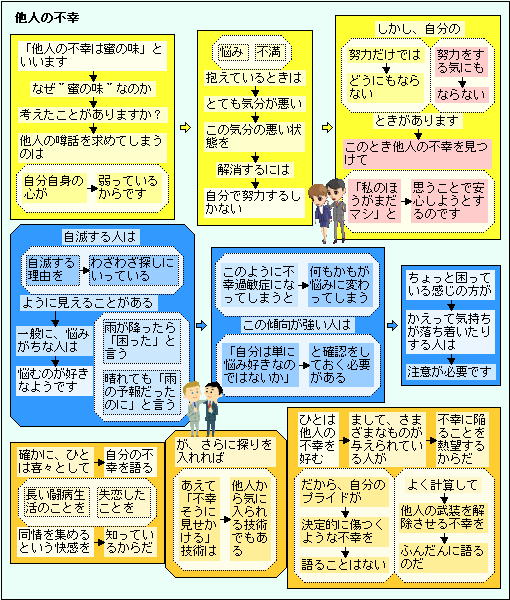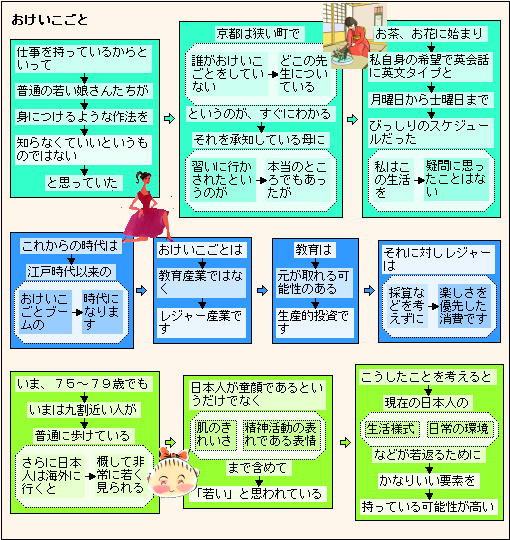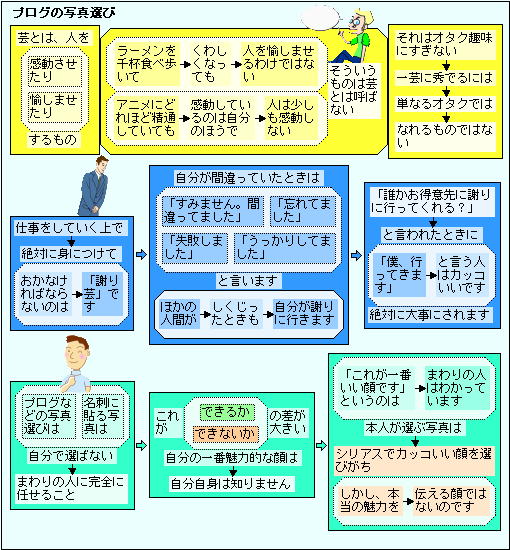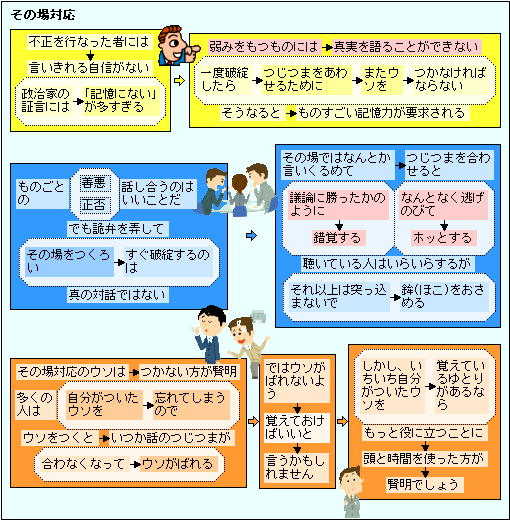子供時代に五感を鍛え、できれば第六感まで身につくようになると良いですね。
第六感まで育つと、「何となく危険」などを察知できるようになるのではないでしょうか。
現代は知識優先の時代になっています。自分が知っている知識、自分が好む知識からでしか納得しません。
感覚が優先していると、その状況に合った知識を受け入れます。その結果、大きな間違いはしなくなるようです!
カテゴリーアーカイブ: 世間
品格なき上司とは?
ツキを呼ぶ、言葉遣い、ビューティーアクション!
「昔はよかった」と、過去というのは都合よく現れる!
同じ内容を話すにも、人により話し方がまったく違うこともある!
「群れをなして行列する」威光を世間にアピールするねらいも!
いま、大学生は大人になりたくないのだ!
人の足を引っぱると、自分もまた同じ運命に見舞われる!
人々は損になるような人とはつき合わない!
旧暦の10月10日(新暦では11月頃)の出雲大社の「神在祭」
水まわりのおそうじをすると!
何気なく暮らして見つける小さな幸せ!
老後の生活費をどうするか?
「非日常」というもの!
思春期は、見た目に最も関心を払う時期!
ほめるときはすぐほめる!
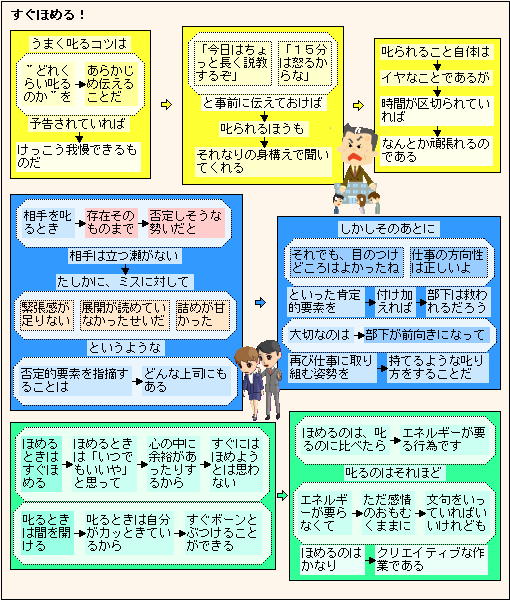
ビックモーターの事件で、叱り方が問題になっています。子供時代に叱られた経験からなのでしょうか?
叱るという場面は、(目下の者に対して)相手のよくない言動をとがめて,強い態度で責める、ということですが、叱ったその先を考えて叱るのが理想なのでしょう。
自分の子供時代の経験から叱るのか、塾考して叱るのか、その人の器が出ますね。
叱ることを考えるより、ほめることを考えた方が、気持ちは楽なのですが、難しいですね!
他人の不幸は蜜の味!
これからは江戸時代以来のおけいこごとのブームが!
プログの写真選びは自分で選ばない!
「自分のことは、自分が一番よく知っている」と思いがちですが、集団の中では、これは通用しません。
社会の中で生活する、ということは、他人の評価の中で生活するということ。それに気づき、それが負担になってしまうと、「とじこもり」になってしまうのでしょうか?
しかし、社会には多様な価値観があります。特に日本は歴史的に多様な価値観を受け入れてきました。神様も仏様も両立してきました。「多様さ=曖昧さ」が受け入れられてきました。
昨今は、ネット検索でAIが利用されるようになり、多様さが除外されがちになってきました。自分で日本語のデータベースをつくり、単語検索すると、日本語の多様さに気づきます。
欧米文化の影響力が強くなり、考え方に多様性(曖昧さ)を失うと、プーチンさんやトランプさんのような人が、受け入れられるようになるのでしょうか!