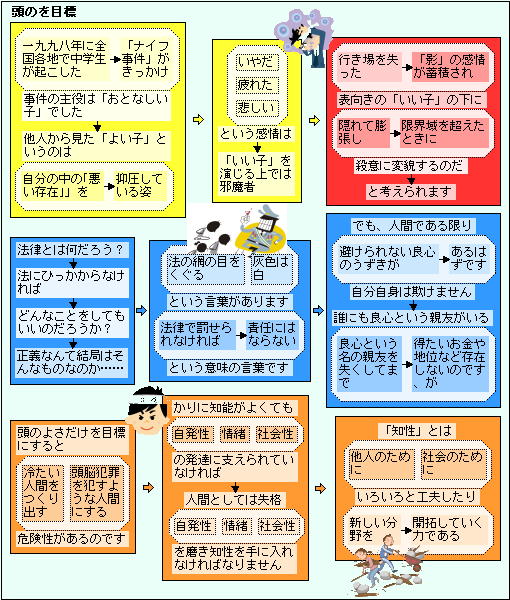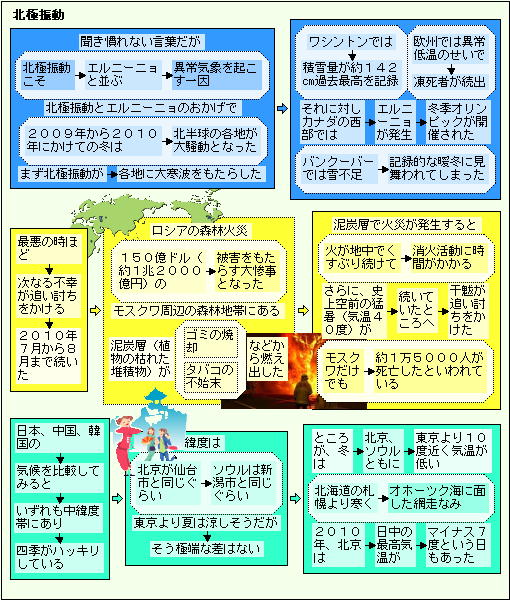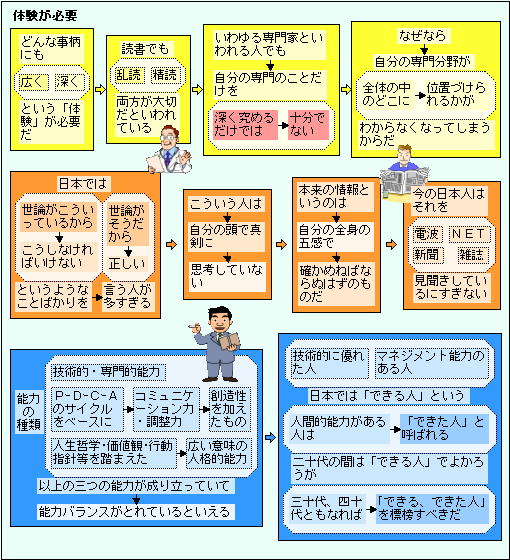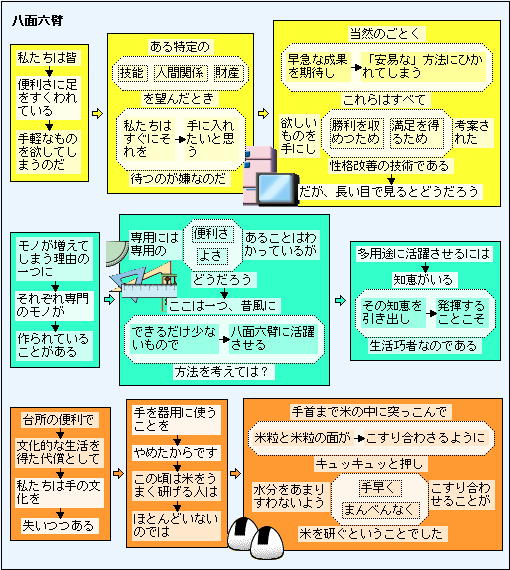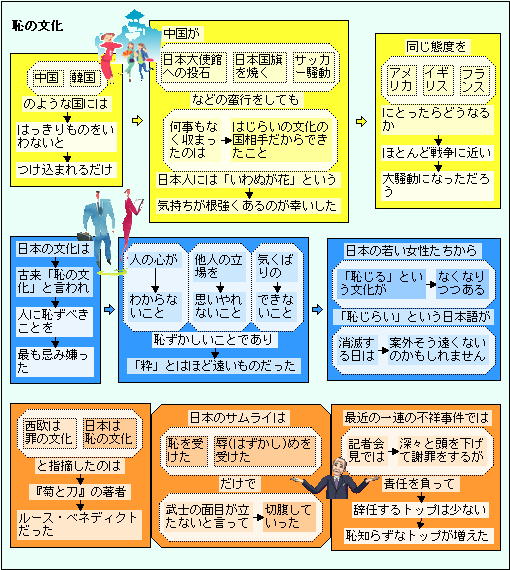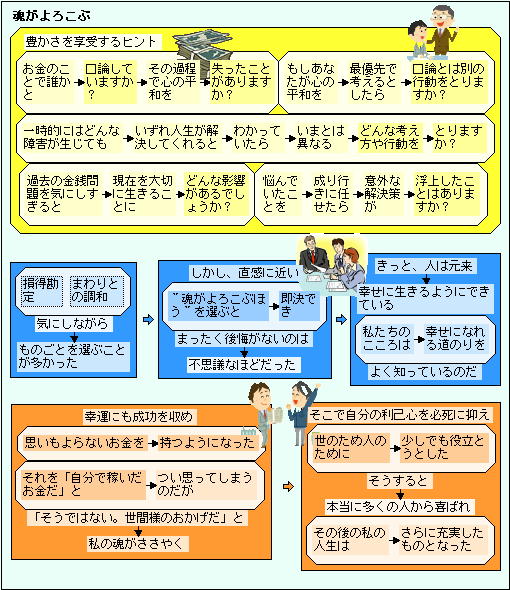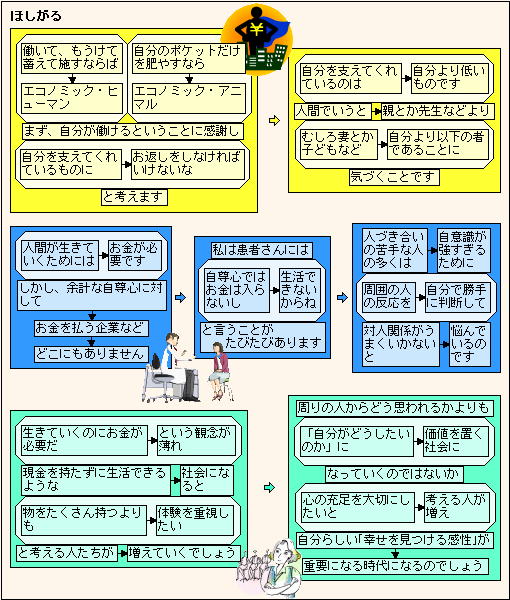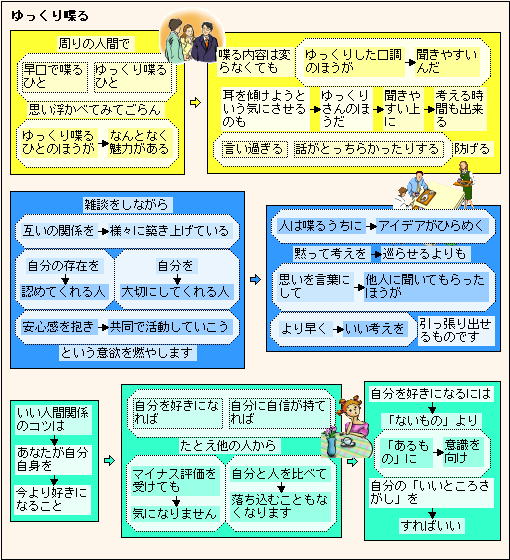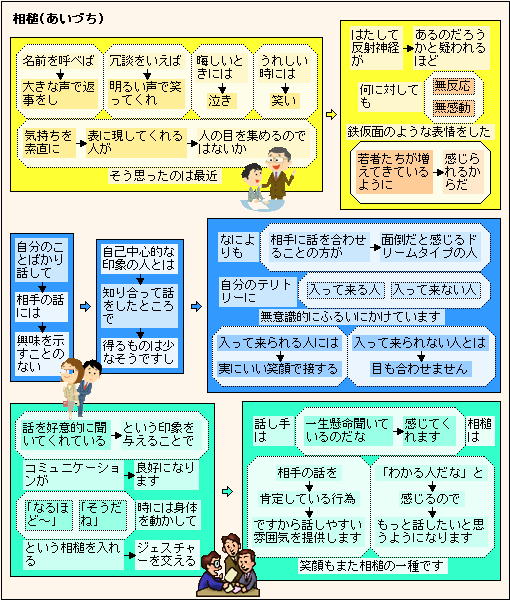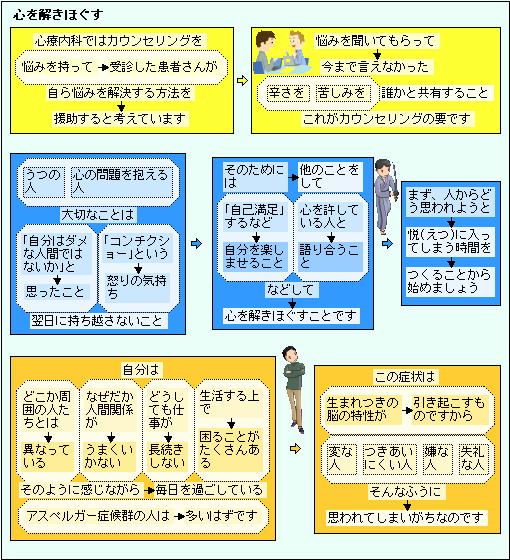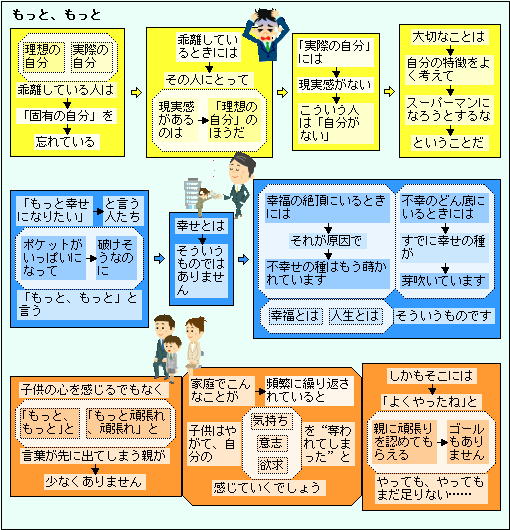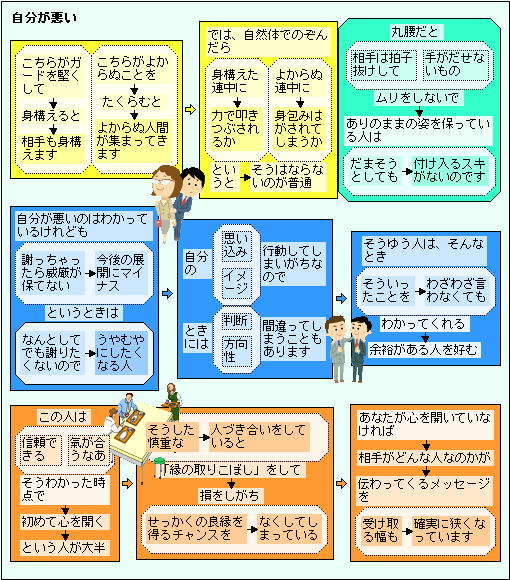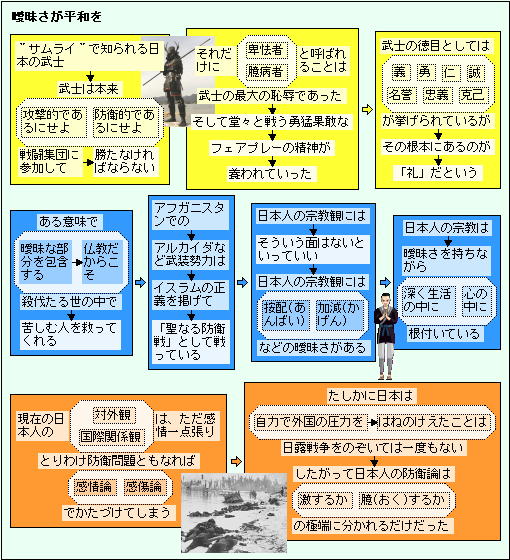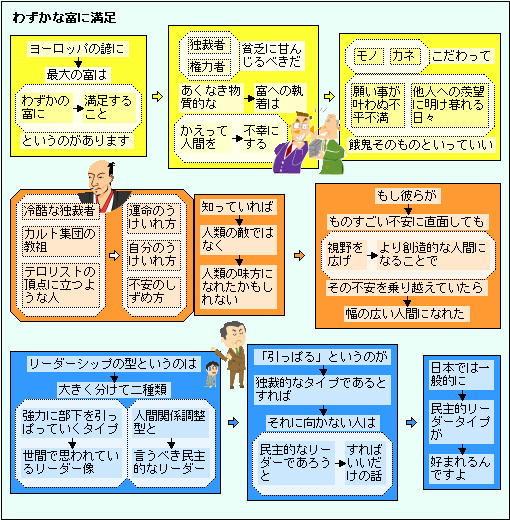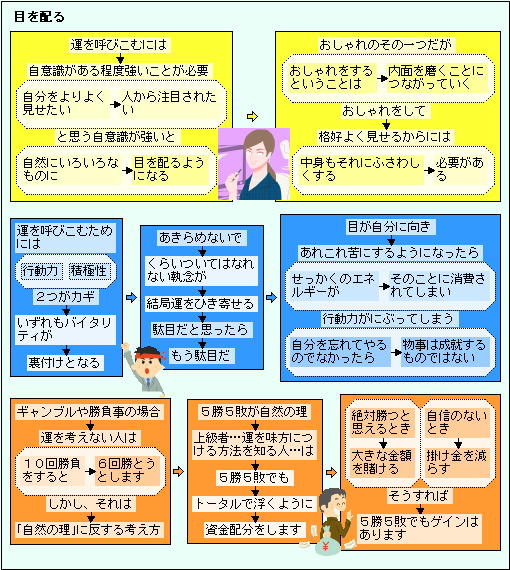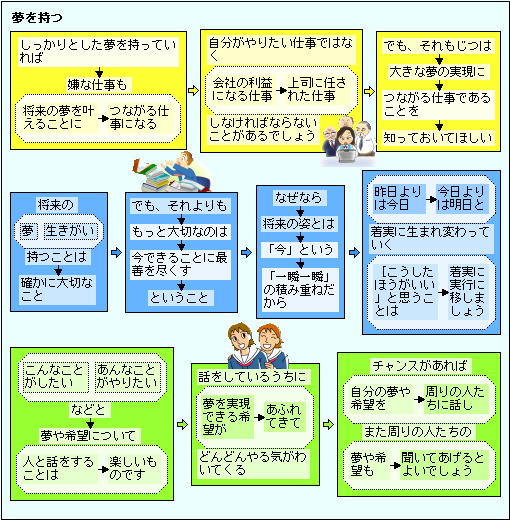NETやスマホを使った犯罪が多発しています。犯罪者は比較的若い人が多いのですが、その人達の親はどのように考えたらよいのでしょうか?
人間の脳が大人になるのは25才程度だそうですが、それまでどのように育てれば良いのでしょうか。
核家族が一般化し、社会で子どもを育てるという感覚が消えてしまい、犯罪者だけ、またはその両親が責任があるという社会になっています。
核家族という社会は、人類が初めて経験している社会体制だと思うのですが、その特性に応じた社会は、いつになったら整備されてくるのでしょうか!
カテゴリーアーカイブ: あたまの散歩
腸内細菌叢の重さは約2kgにもなる!
日本人が長寿なのは素足でいることが多いから!
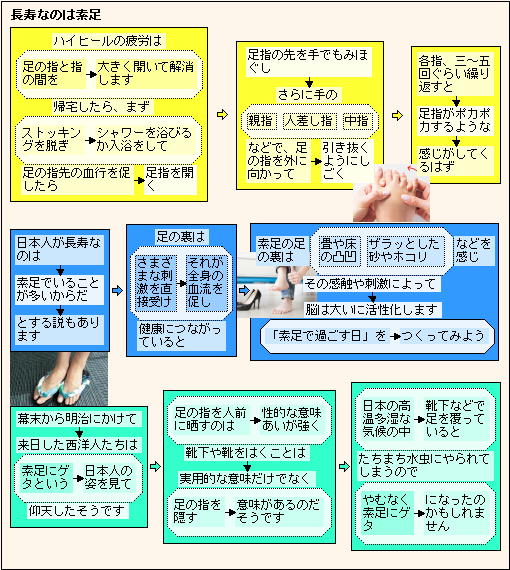
靴に小さな石が入ると、足の裏は直ぐ痛みを感じます。足の裏はすごく敏感ですね。私の小学校からの友達が、中学に二年の時高熱が続き、視力を失いました。その友人が言っていたのですが「足が目の代わりだよ」といって靴の底で地免を探っていました。
足の指を使っていますか?
足の親指側に力を入れると、足の内側の筋肉に力が入ります。足の小指側に力を入れると、足の外側の筋肉に力が入ります。
膝に人工の関節を入れた人が、足の指に力を入れることを意識して歩くようにしたら、ずいぶん楽になったと話しておられました。
冬場はポケットに手を入れて歩きがちなので、足のそれぞれの指の力加減でバランスをとりましょう。脳の活性化につながるかもしれません!
頭のよさだけを目標にすると!
高校までに法律を学ぶ機会は多くありません。憲法は若干学ぶのですが、商業高校以外では、民法や商法を学ぶ機会はほとんどありません。
私は商業高校だったので、民法と商法の学課がありました。両方とも同じ先生だったのですが、最初の学習の場面で、「法律は最低のマナーだから………」で始まりました。この意味は、最低のマナーを守ればよいではなく、もっと上のマナーを目指せ、という意味で理解しました。古くからの商人の町でしたから、長く商売を続けて行くには、法律を守るだけではやっていけない、という意味も含んでいたのでしょう。
立法を行う国会議員すら、最低のマナーである法律を守れない人もいます。国会での質問以外では、名誉毀損になりそうな質問をしている議員もいます。これらを見習ってしまうと、見習った人の人生は、終わってしまいかねないですね!
北極振動も異常気象を起こす一因!
広く、深くという「体験」が必要だ!
少ないもので八面六臂に活躍させる!
日本古来の「恥の文化」は!
日本は「恥の文化」と言われています。自分の価値観より、周りの価値観の方が重要です。これは災害が多い社会で生きるための知恵なのでしょう。
しかし、災害がここ数十年は少なかったので、平和ボケしてしまい、恥の文化の説得力は少なくなりつつあるようです。
ただ、これからは災害が増えてくる雰囲気があります。電気が止まり、水道が止まったとしたら、水はどのようにしかすか?
たとえ給水車が来たとしても、運ばなければなりません。お年寄りや病気の人、女性の人、二階や三階ならともかく、それより高い階にお住まいの方は、男性でも大変です。飲み水くらいならなんとかなりそうですが、それ以外は助け合いがなければ難しいですね。
やはり、周りのある程度配慮しtた生活スタイtるは必要なのでしょうね!
"魂がよろこぶほう"を選ぶ!
物をたくさん持つよりも体験を重視!
雑談をしながら互いの関係を築く!
相槌は、話を好意的に聞いてくれている!
まず、心を解きほぐす!
「もっと、もっと」と!
なぜ、自分より下の人や子供に、「もっとガンバレ」と言ってしまうのでしょうか?
取り組み方を、具体的に「こう考えれば……」と方向を示す言葉が必要なのでしょうね。
知識教育が進んだ結果、自分でいろいろな情報を五感で収集し、それをもとに対応策を考える人が少なくなってしまいました。むかしのように「やって見せて、見て盗め」が成立しにくくなっています。
知識は、基本的には過去のもの、そして、何かしらの資料、あるいは測定が出来るもので成り立っています。
最近、研究者の方のラジオ番組を文字化しました。それと、その研究者の方の本を読んでみると、ラジオの方が参考になりました。
本は、既に確定したものを修飾した表現になっています。しかし、ラジオでは「……かもしれないですね」という情報も含まれています。多少曖昧でも、それで良いのでは、と思います!
悪いのはわかっているけれども!
殺伐たる世の中で「曖昧さ」が平和を!
まず傾聴することに専念すること!
最大の富はわずかな富に満足すること!
自然にいろいろなものに目を配る!
自然にいろいろなものに目が行くようになると、気づきが多くなります。
例えば、ホームページだ町を紹介する写真を撮っていると、カメラを持たないで歩いているとき、あるいは、クルマを運転しているときなどでも、自然に周りに目が行きます。
また、いろいろな歩き方をテストしていると、足の使い方だけでなく、腰の動き方や上半身の動きなどにも目が行きます。高速道路のパーキングエリアの人達の歩き方、坂が多いところに住んでいる人達の歩き方など。
それに加え、サッカーでボールを蹴るとき、テニスや卓球でラケットでボールを打つとき、これらは足と腰と手と、肩が右側(あるいは左側)が同一方向に動いています。むかしの「ナンバ歩き」のようなからだの使い方のようです。
興味の範囲を広げ、自然に、いろいろなものに目が行くようにしておきたいものです!