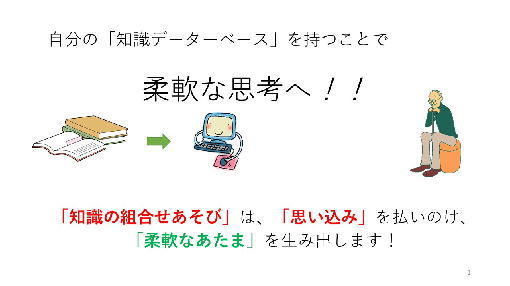下半身の筋肉の減少が、高血圧にもつながっているとのこと。下半身は、血液のダムでもあるのですね。本物のダムは、砂が溜まって容量が減るのですが、下半身は、筋肉が減少して容量が減るのですね。ウォーキングとともに、こまめに動くことが大事なのでしょう。飽きが来ないよう、その土地の歴史、伝説、言い伝えや、神社などの古い建物と地形との関係など、長続きするように、プラスαの工夫をしましょう!
カテゴリーアーカイブ: あたまの散歩
五感が発達していない人が増えている?
言葉に五感を植えつけないと!
子供時代に、五感を通して言葉を学ぶ、という経験が少なくなっています。核家族もその一因、両親は子育てで、言葉で「言うことを聞かせる」ことが中心になってしまいます。しかし、祖母や祖父は孫達に、その場に応じた(五感に応じた)声かけを行います。この経験があると、ある単語を聞いたとき、その場面を五感を伴って思い浮かべることができます。また、スポーツでも、子供時代からクラブに入り、大人から言葉を中心とした指導を受けるようになっています。草野球といった年齢の違う子供達が、自分のできることを見つけながら遊ぶ、といった環境もなくなってきています。五感を伴うことが少ない言葉の世界は、言葉による理論が先行し、辛くなることも多いのでしょう!
夜型が定着してしまった人も!
源平の合戦に携帯(伝書鳩)が使われていた?
立秋、秋の気配が漂ってくる!
「断食」で身体の声を聞いてみる!
韓国の「他者中心」の生き方!
人間関係は鏡のようなもの!
怒り出したら心の中で「1、2、3……」と!
表情で、きれいにも、チャーミングにも!
重要な意志決定は午前九時から十一時に!
ネガティブな思いにとらわれる!
今年のように、お盆の時期に台風が来てしまうと、予定が大きく狂ってしまいます。ここは「神様が、エネルギーを使いすぎだよ」と警告している、しょうがないと、むかしの人は考えたのでしょう。「雷神」という神様がいます。雷神は人びとを恐怖のどん底に突き落とす崇り神様ですが、一方で、雷神が稲穂と交わることで、稲は実を結ぶと信じられていました。実際に、空気中にある窒素(空気の80%)に、雷=電気が流れると、窒素酸化物になり、これが雨に溶けて降り注ぐことで作物の肥料になります。このように、日本の神様には二面性があります。ただ、昨今の人々には、「自分だけが正しい(思い込み)」、という一面だけの人が増えているようですね。世間の犯罪を見ると!