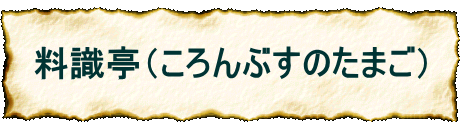| 肥満には遺伝的な要素も関わっています! | ||
| 2025年 12月25日 (木) |
歴史では、朝廷の金銭問題はそれほど取り上げられないですね。 朝廷の財政状態の推移や、お寺や神社の財政問題、かなり苦しい時代もあったのでしょうね。 苦しい時代を乗り切るための、ビジネス感覚が重要だったのでしょうね。 しかし、それらはほとんど語られないですね。 「墓じまい」が高額になっているのも、そのような事情があるのでしょうね! |
|
| 神功皇后を祀る神社が多い住吉大社! | ||
| 2025年 12月15日 (月) |
他人のアドバイス、それを採用するかどうかは自己責任、しかし、他人責任にしてしまいます。 ネットの誤情報も、自己責任と考える人は少ないようです。 そのためか、誤情報でも拡散してしまいます。 豊臣秀吉も、「織田信長は死んではいない」という誤情報で、明智光秀に勝利しています。 そのような背景が京都に根付き、京都では言葉通りに受け取らない風土があるのでしょうか? |
|
| 招き猫発祥の地「豪徳寺(東京)」! | ||
| 2025年 12月9日 (火) |
「縁起」を考える時期が地下図いてきました。 有名なのは「招き猫」、でも最近はあまり見ないですね。 でも、七五三では神社で子ども連れで参拝している家族を見掛けます。 子どもに対しては、縁起の催しはまだ残っているようです。 正月の食べ物は、その多くが冷凍の「おせち」になっているのでしょうか? |
|
| 千年の木は、柱になってもさらに千年、生きる! | ||
| 2025年 11月15日 (土) |
オーバーツーリズムで、京都や奈良の修学旅行が難しくなってきています。 日本の古い木造建築を見るチャンスが失われています、 しかし、京都や奈良以外にも古い木造建築があるのですが、なかなか集中した場所にはありません。 鎌倉も神社仏閣は多いのですが、国宝の建物はあまりありません(観光客は増えているのですが)。 大人になれば、少し離れていても、あちこち尋ねることが出来るのですが! |
|
| 「倭冠」は日本人の海賊集団? | ||
| 2025年 11月1日 (土) |
他人の利益をまったく考えようとしない人、自分のカラのなかに閉じこもってしまう人、これだと「人を動かす」には大変です。 その対策として、「報酬を与える」という方法が生まれたのでしょうか? 報酬を一部の人に与えると、争いのもとが生まれてきます。そして、その争いを抑えるため武力が生まれたのでしょうか? 多くの人達の利益を優先するため、民主主義が生まれたのでしょうか? |
|
| 「お月見」一年に二回する習慣があるのは日本だけ! | ||
| 2025年 10月28日 (火) |
冬になると、見通しの良い時期が続くので、「星見」に移っていくのでしょうか? 見通しの良い夜に、空を眺めていると、心の雑念も晴れてきますね。 春の種まき・夏の手入れ・秋の収穫までは、仕事がいそがしいので、秋が終わり頃になると、やっと心に余裕ができ、また、雑念もでき、心を晴れやかにする必要があったのでしょうか。 春が来るまでは、夜空を楽しむことが出来ますね! |
|
| 地蔵人気は、平安時代、地獄の恐怖心が強くなったことで! | ||
| 2025年 10月12日 (日) |
お寺の入口や道端で見掛ける地蔵菩薩。閻魔大王の裁きで地獄に落ちないように救ってくれる地蔵菩薩。 平安時代に、富士山の延暦大噴火(800年頃~)と貞観大噴火(864年~)が代表的ですが、この恐怖に対し地蔵信仰が盛んになったとのこと。 いま、富士山の噴火が起こるのではないか、すると、電子機器が障害を受け、交通機関だけでなく情報社会も壊滅的な障害を受けるのではないか? との恐怖心が起きても致し方ない時代になっています。 なにか救いの菩薩が現れるのでしょうか? |
|
| 古代エジプト文明の多神教の伝統に帰ってはどうか! | ||
| 2025年 8月1日 (金) |
最近のイスラムの行動を見ていると、なんとなく「ヒトラーがユダヤ人に対し異常な人種的偏見を抱いた」のが、分からないでもないような気がしてきました。 ユダヤの格言『一度に海を作ろうと思ってはならない。まず小川からつくらねければならない』は、そうでないため格言になっているのだろうか、と思ってしまいます。 一神教の国々は過激になりやすいようですね。自己中心になりやすいのでしょうか?M 多神教の国でも戦争の歴史はありますが、一神教の国よりは少ないのでしょうか! |
|
| 桃太郎は、イヌ(信頼)・サル(知恵)・キジ(情報)を連れて鬼退治に! | ||
| 2025年 4月29日 (火) |
桃太郎の伝説、吉備の国(第四十一代持統天皇の時、吉備の国は備前・微衷・備後・美作:主に現在の岡山県と広島県東部)の伝説です。 意外と知られていないのが、「鬼を殺したりしません。 悪いことは悪いときちんと教えるけれど、反省したら許しています」。 日本の文化の基本に、このような考え方が根づいていたのですね! |
|
| 河童の原型は太古から、明確なイメージが誕生したのは近世! | ||
| 2025年 4月21日 (月) |
カッパは想像上の生き物ですが、太古の時代からいたようです。 水は人間にとって(作物にとって)非常に大事なもの、しかし、災いも起こします。 この災いがカッパを生んだのでしょうか? 日本、とくに関西から西はそれほど大きな川が少なく、まだよかったのでしょうが、東日本は大きな川があり、大災害も多かったのでしょうね。 でも、中国ほどの大河はなかったので、竜までは生まれませんでしたね! |
|
| 騎馬遊牧民が最初にあらわれたのは、紀元前1000年頃! | ||
| 2025年 4月15日 (火) |
移動しながら食料を入手していく、という生活スタイルと、一定の場所に定着し生活するスタイルとでは、戦にどのような違いが生まれたのでしょうか? いわゆる遊牧民と農耕民の生活スタイルの違いなのですが。 戦いの武器については遊牧民が圧倒的に有利ですが、戦いを続けるための補給体制では、農耕民続報が有利と思われます。 人類の長い歴史を見ると、どちらも生き残っているので、同等なのでしょうね! |
|
| 朝鮮半島は、西暦300年代に独立の国づくりが進んだ! | ||
| 2025年 3月28日 (金) |
朝鮮半島の歴史は、紀元前200年頃に中国の一派が移り住んだことから国づくりが始まったようです。 日本の縄文時代や弥生時代の時期の国づくリは、どのような状態だったのでしょうか? 日本の歴史では、西暦300年代(古墳時代)から600年代(飛鳥時代)にかけて、ヤマト政権(大和朝廷)による統一・建国がなされ、今に続く日本の基礎ができたとされています。 遣隋使は西暦600年~618年の18年間に3回から5回派遣されています。 目的は国づくりのためなのでしょうが、「国づくり」という意識はその前からあったのでしょうから、いつごろからなのでしょうね? |
|
| 江戸時代の吉原、いろいろな文化を生み出した! | ||
| 2025年 1月19日 (日) |
江戸時代の吉原は、江戸の文化を創り出していたのでそうね。 テレビなどで見ると、花魁が高下駄を履いて町を練り歩いている画面を見ます。 現在は、一般の人では歩き方を学ぶことはほとんどありません。 乗り物が普及したためでしょうか。 いまでも歩く姿を注意深く見ていると、車が使えない坂の上に 子供時代から暮らしている人は、足を前に出す筋肉の使い方が違っているようです。 腰などの動き方が少し違っています! |
|
| 大晦日に蕎麦を食べるようになった由来! | ||
| 2024年 12月28日 (土) |
日本の伝統的な行事は大切にしたいですね。 欧米の文化が浸透したため、つい、昔からの行事を忘れてしまいます。 日本の行事は、何かしらの災害時でも「つながり」を維持し、災害時に助け合う風土づくりに貢献していると思います。 「ボランティア」という言葉が使われていなかった時も、日本には助け合う風土が根づいていました。 その助け合う気持ちを維持し続けるため、いろいろな行事が生まれたようです。 行事は、神様や仏さまとのつながりが強いのも、そのためではないのでしょうか! |
|
| クリスマス、ふと考えてみるきっかけに! | ||
| 2024年 12月24日 (火) |
日本では行事が少なくなりつつありますが、いろいろな行事があると、それぞれの行事の成り立ちや目的を、ふと考えてみるきっかけになります。 災害が多かった日本、行事がたくさんありました。 それも、地域それぞれ風土が違うため、各地に個性のあるいろいろな行事が生まれたようです。 それらの行事は、災害に遭った人々が、立ち直るきっかけにもなったようです。 50年前のお年寄りの子供時代の記憶には、生活に根づいた行事は、たくさん残っていたようです。 歴史を大切にする日本、残念ですね! |
|
| おせちは、神前に料理を供え、お下がりを食べたのが始まり! | ||
| 2024年 10月29日 (火) |
おせち料理の予約時期になっています。 一方で、忘れられていく年中行事もあります。 地域によって違いますが、お正月だけでも、三が日、七草がゆ、山の神、蔵開き、せいの神、えびすさまなどに、お供えしたり、お祈りしたり、いろいろな行事を行っていたようです。 お雑煮でも、地域によって、各家によって、それぞれの作り方がありますね。 それぞれに、意味づけし、その継続に腐心していたようです。 そのようなことが、日本の風土をつくり、それぞれの地域での暮らし方を工夫してきたのですね! |
|
| 聖徳太子が実在の人物ではなかったという説が! | ||
| 2024年 9月9日 (月) |
誰も知っている、日本古代の偉人「聖徳太子」、近年、「聖徳太子が、じつは存在しなかった」という。 教科書表記にも影響を及ぼすほどになっています 教科書では、いままでは「聖徳太子」と書かれていたのですが、最近は「厩戸王(聖徳太子)」とカッコつきの表記に変わってきています。 「聖徳太子」と私たちが呼んでいるこの名前は、彼の本名ではありません。 これは彼の功績を称える人々が、後世になり彼に贈った名前で、贈られた人物の名は「厩戸王(うまやとおう)」。この「厩戸王」は実在の人物です。 |
|
| 渡来人がもたらしたいろいろなものをアレンジした日本! | ||
| 2024年 5月26日 (金) |
日本は、外国から入ってきた文化に、日本のアレンジを加えることが殆どです。 中国や朝鮮半島で政変が起こったとき、日本に亡命してくる人達が少なくなかったようです。 亡命してきた人達は、日本の自然条件がかなり異なるため、材料や流通ルートも異なってしまいます。 そのため、日本の人達と一緒に工夫し、日本で採れる材料をもとに、運びやすく、長持ちする商品を作ってきたのでしょう。 そして、和食の文化を育ててきたのでしょう。 そのやり方が他の産業にも普及し、日本独自の文化を創り上げたのでしょう。 もっと、日本各地の自然環境にあった文化を大事にしたいですね! |
|
| 獲物は全員に分けられていました! | ||
| 2024年 5月18日 (土) |
「総ての財産を共有する」、「貧富の差が無い社会をつくる」という共産主義。どこへ行ってしまったのでしょうか? 日本でいえば、縄文時代の生活スタイルなのでしょうね。 アフリカの食べ物が豊かな地域では、分け与える風土がいまでも残っているのでしょうね。 日本では、四国巡礼の「おせっかい」のような風土ですね。 日本でも何かもらい物をしたとき、直ぐお返しをする地域と、お返しをあまり気にしない地域があります。 このような風土はやはり自然環境から生まれたものなのでしょうか。 しかし何であれ、「感謝の気持ち」は、忘れてはならないですね! |
|
| 調和をたいせつにする日本人の美徳! | ||
| 2024年 4月14日 (日) |
日本人は、「和をもって貴しとなす」が社会に根づいています。 自己主張し過ぎると敬遠されます。 そのためか、日本語の「曖昧さ」が通用しています。 その背景は、台風や地震、干ばつ、洪水などの自然災害が多く、逃げる場所も無く、助け合いを行わなければ生存できませんでした。 生物の生き残りの原則は「助け合い」です。 それを継続・定着させるのが「風土」です。 現在、外国との接触が増え、日本の学校では外国語教育が拡大しています。 しかし、「和をもって貴しとなす」は、壊さないでほしいですね! |
|
| 日本の古い社会は出来損いを見事にとりこんだ! | ||
| 2024年 3月29日 (金) |
現代は多様な人達が、社会から認められようとしています。昔の日本がそうでした。 平安時代の中頃までは、中国や朝鮮半島から、政権を失ったり、政権から阻害された人達が、日本に流れて来ていたようです。 また、山に囲まれた地域や、島に住んでいた人達も、その土地になじめないと他の土地に移っていました。 文化や風土が異なる人でも、容易に受け入れる場所があったのでしょう。 そんなむかしの日本が、また、復活してきているのでしょうか! |
|
| 食べたくても食べられない! | ||
| 2024年 3月3日 (日) |
むかしは、ヨーロッパは食糧不足問題から戦争が当たり前になり、その風土がいまも続いているのでしょうか? 我々から見ると、戦いに寛容のように見えます。 またアフリカも、人類発祥の地でありながら、アフリカに残った人達も食糧事情が悪いのか、争いが絶えないですね。 今は地球の人口が増加傾向にあり、ますます争いが増える傾向にあるのでしょうか? |
|
| ロシアの楽しみは、現在ではなく未来にある! | ||
| 2024年 1月31日 (水) |
ロシアで「睡眠学習法」という実権が行われていたそうです。 良いほうに解釈すれば、自分を肯定的にする、という実権なのですが………。 録音テープに、自分を肯定する言葉を録音し、そのテープを睡眠の始めに流し洗脳する実権です。 ロシアの風土を考えると、反政府的な人を生み出さないためでは、と思ってしまいます。 ロシアは、帝国の段階から、反国家の人達をシベリア送りにしていました。 また、『シベリア抑留記』(原田道之助の手記)から感じるロシアの風土からも、良いほうには受けとれません。 そのような風土だからこそ「反戦争」や「未来に夢を持つ」といった内容の小説が書かれているのでは、と思ってしまいます! |
|
| 世界のどこにもそれなりの特殊性がある! | ||
| 2024年 1月29日 (月) |
国や地域には。それぞれに特性があります。 しかし、情報化社会では、情報発信力の強い地域が、世間の常識としてとらえられます。 すると、それぞれの地域の特性に、気がつかなかったり、無視されます。 日本では、西日本と東日本では、地域の特性に関する気づきが違うようです。 例えば、関西の大阪・京都・神戸・奈良など、それぞれの街の特性に違いがあると思っています。 関東はどうでしょうか。東京・川崎・横浜・千葉・埼玉など、違いをどの程度意識していますか? 外国を見る場合、日本の感覚で見ていると、思いがけない勘違いをしてしまうことが、あるのでしょうね。 ロシアを見る場合はどうなのでしょうか? 日本の戦国時代のように、領土を拡大した者が英雄だった時代の感覚で、見た方が良いのでしょうか? |
|
| お地蔵さんのそばを通りすぎるときに! | ||
| 2024年 1月19日 (金) |
古くからの街では、お地蔵さんをお寺の入口や道端でよく見掛けます。 六地蔵もお寺ではよく見掛けます。六地蔵は地獄・餓鬼・畜生・修羅・人道・天道の六道を能化する有難い佛様として昔から信仰されています。 また、多くの罪人たちが首を斬られた処刑場であった場所に、その供養のために、六体の地蔵が建てられたのが、六地蔵のはじまりであるとの伝えもあるようです。 お地蔵様は、天国に対する地獄の存在が強く意識されはじめると、一般民衆にもそれが浸透し、人々は、 「死んで地獄に落ちたら、どうすればいいのだろう……」 「地獄での苦しみから救ってくれるものがあるのならば……」 と、いう想いで、お地蔵さまに救いを求めるようになっていったとか。 |
|
| 神社にある狛犬は外国からもたらされたもの! | ||
| 2024年 1月5日 (金) |
狛犬は、平安時代には宮中に対(つい)で配置されていたと言います。 そのためでしょうか、尾道の市役所の前に、建て替えられる以前は大きな狛犬がいました(建替後はいなくなってしまいました)。 鎌倉時代以降、神社での前に置かれるようになったのですが、神社によっては狛犬が居ないところもあります。 何か基準があるのでしょうか? |
|
| なぜおみくじを木の枝に結ぶのか! | ||
| 2024年 1月3日 (水) |
神社に行くと、おみくじがたくさん木に結びつけられた神社に出会います。 この神社のおみくじは、凶が多い神社なのかな? と思ってしまいます。 おみくじに凶が出たとき、木に結び、神様のお許しや加護を得るためだそうです。 凶をたくさん出した方が、その神社の信仰が強くなるため? なのでしょうか! |
|
| 中央アジアにはかつて日本人も数万人いた! | ||
| 2023年 12月24日 (日) |
ロシアのウクライナ侵略に、嫌悪感を持つ人が多いと思います。 日本人の感覚では理解できません。 しかし、トップがやることの「良い」か「悪い」かを、判断してはいけない国もあることを知っていなければ、世界情勢は理解できません。 ロシアの歴史は、トップに反対する人間は、暗殺するか、シベリア送りにするか、の歴史のようです。 たとえ間違っていても、自分の意見を言ってはならない国のようです。 第二次世界大戦後、シベリアに長く抑留された日本人の、当時の様子を知ると、「言われていることしかやらない」という風土が、定着しているようです! |
|
| 草や木という生き物ばかりでなく山や川にも神が! | ||
| 2023年 12月20日 (水) |
日本には、自然の恩恵に感謝し、自然の中に神が宿っている、という考え方が受け入れられています。 「人」が神様扱いされると、戦争という危険が生じてしまうようです。 日本も、人が神様扱いされるようになると、戦争が起きています。 西洋ではキリストという人が神様扱いになっています。中東のムハンマドもそうです。 「自然に神様が宿る」が主になっていると、平和な時代が続くようですね! |
|
| 緊急事態は突然やってくる! | ||
| 2023年 11月24日 (金) |
宗教は、建て前は精神世界ですが、実態は「お金」で考えなくてはならないようです。 やはり、ビジネス感覚が重要です。それに精神世界が取り入れられ、多額のお金を集めるしくみ、そして、子孫代々に続くしくみ、これが受け入れられたとき、大きな宗教団体ができるようです。 イスラム教もそうですが、日本では一向宗も年貢を納めず、自主的な運用で100年に及ぶ自主運営ができていました。 宗教活動にすれば、法律の適用が甘くなることも取り入れていますね! |
|
| 昔の木造家屋はマイナスイオンを増やす! | ||
| 2023年 11月10日 (金) |
昔の建物は、自然に適応し、自然の効果を生かす工夫がありました。 昔の家屋はまだ残っているので、いろいろな研究ができます。 また、現代の建物に取り入れる工夫も、少しづつ生まれているようです。 昔の子育てにもいろいろと工夫があったようです。 ガキ大将が、いろいろな遊びを教える中で、安全を自分達でどのように確保していくか、大人に聞きながら、自分達で考え、また、小さな子供達に分かるように、体験しながら教える知恵がありました。 この知恵は、単に教わるのではなく、自分で考え、テストし、対策をつくり上げていました。 しかし、こんな体験をした人は、どんどん少なくなっています。 また、核家族化し、孫達に伝えることもなくなっています、積極的に取り入れる子育て組織もあまりないようです。 数十万年の人間の子育ての歴史が、消えてしまうのでしょうか! |
|
| 国境を越えてくる宗教が! | ||
| 2023年 10月27日 (金) |
世界の宗教の60.3%を占め、三大宗教と言われるキリスト教、イスラム教、仏教。 しかし、日本では確かにお寺さんは数多くありますが、本当に仏教徒なのでしょうか? 神社もたくさんあります。しかも、生きているときのお願い事は、どちらかというと神様にお願いします。特に将来の希望は、神様にお願いしています。 むかしはお寺さんも、狩猟・漁師・商人など少し身分が低く見られていた人が、豊かになってくると、その人達を救う手立てを考え、仏教を広めていました。 室町時代の末期から戦国時代、北陸の一向宗などは100年も自主的な政治を続けていました。 現代の仏教ビジネスを再考しなければならないのでしょうね! |
|
| 人頭税廃止で拡大したイスラム教! | ||
| 2023年 10月25日 (水) |
宗教を広めるには、ビジネス感覚が必要なようです。 広めたい階層(お客)に、どのようにして広めるか(売りこむか)。 ・イスラム教は、人頭税という税金の免除。 ・大航海時代のキリスト教は、武器・弾薬を含む貿易。 ・浄土真宗の一向一揆は、戦国大名からの税の徴収を拒める不入の権利。 広めたい階層に有利な権利を確保しながら、思想を定着させ、末永く継続すること(老舗)を目指す、という手法のようです! |
|
| ユーモア・ジョーク、機転を身につけるには! | ||
| 2023年 10月7日 (土) |
ユーモアやジョークを言える人は、視野が広く、固定観念がなく、経験が豊富だけでは、言えないですよね。 それにプラス「機転」が必要ですね。 また、風土も関係しているようです。 よく大阪の人はおもしろい、と言われています。 子供の時から、状況をつかみ、なにかしら視点を変えて言う、という風土があるのでしょうね。 川や海、台風や地震といったものに、権力争い、いくさ、それに貿易や商売など、歴史的な風土も影響しているのでしょうね! |
|
| 古代の人類は太陽信仰みを持っていた! | ||
| 2023年 9月23日 (土) |
自然信仰や先祖を敬う信仰が少なくなってきています。 もちろん国によってかなり違いはあるのでしょうが、自然に学び、自然を大切にすることは、人類の生き残りの期間を延ばすことにつながっているのでしょう。 ただ日常では、ついついエアコンを使い、蓄電池つきの電化製品を使ってしまいます。 どうしてなのか、コード付きの電化製品ですむ場合でも、蓄電池つきの電化製品になっています。 この無意識が温暖化につながり、人類の生存期間減少に影響を与えるのでしょうね。 これを救うのは、太陽信仰や自然信仰なのでしょうが、これを取り戻すことは出来るのでしょうか? |
|
| 日本は複雑な人種を混入させながら1つに! | ||
| 2023年 7月27日 (木) |
日本には7世紀ごろまで、渡来する人達を受け入れており、その人達と協力し「日本人」というものをつくってきました。 「日本は単一民族国家である」は、政治的に同化政策が必要なときに、発信されたようです。 「曖昧な風土」が許容される日本、7世紀頃までは渡来人が多くいたようです。その人達を含め、協力して、日本文化を、そして、日本人を育ててきました。 移民しても、自国だけの文化しか許容しない民族もいれば、移民先に馴染もうとする民族もいます。 食糧事情が許されるのであれば、外国の人達を多く受け入れることも必要ですね! |
|
| 花火は夏のビッグ・イベント! | ||
| 2023年 7月25日 (火) |
都市部の祭は夏ですね。 農作地帯は秋の終わり頃のようです。 でも、最近の御祭は、お客さんの中には、自己管理があまりできなくて、安全対策に多くの費用がかかるようです。 将来も御祭を継続して行くには、どこかで、事故の責任の多くは、お客が責任を持つことにしないと、御祭を続けていけないのでしょうね。 庶民の文化は、継続していかないと、ロシアのような風土になりかねないですからね! |
|
| 神道の“自他一如の法則”という教え! | ||
| 2023年 6月29日 (木) |
智慧は、学問的知識や頭の良さの発揮と思われがちですが、そうではないようです。 辞書によると「人生経験や人格の完成を俟(ま)って初めて得られる, 人生の目的・物事の根本の相にかかわる深い知識。叡智(えいち)。」とのこと。 具体的には、「誰にも親切にする」と思った方が合っているようです。 相手の立場で考え、相手のメリットになりそうなことが出来ることが「智慧」と、思った方がよいようです! |
|
| 日本古来の「恥の文化」は! | ||
| 2023年 1月26日 (木) |
日本は「恥の文化」と言われています。自分の価値観より、周りの価値観の方が重要です。これは災害が多い社会で生きるための知恵なのでしょう。 しかし、災害がここ数十年は少なかったので、平和ボケしてしまい、恥の文化の説得力は少なくなりつつあるようです。 ただ、これからは災害が増えてくる雰囲気があります。 電気が止まり、水道が止まったとしたら、水はどのようにしかすか? たとえ給水車が来たとしても、運ばなければなりません。 お年寄りや病気の人、女性の人、二階や三階ならともかく、それより高い階にお住まいの方は、男性でも大変です。 飲み水くらいならなんとかなりそうですが、それ以外は助け合いがなければ難しいですね。 やはり、周りのある程度配慮しtた生活スタイtるは必要なのでしょうね! |
|
| 因幡(いなば)の白ウサギの話! | ||
| 2022年 12月31日 (土) |
「因幡の白兎」に登場するウサギは、嘘がバレると「酷い目に遭う」と。 イソップ物語の「カメとウサギ」では「気を抜くと負けてしまう」となっています。 欧米では、ウソであろうと本当であろうと「最後まで自分の主張を貫け」ということのようです。 日本では、嘘をつくと社会から除外されてしまうので、「ウソはつくな」ということになっています。 日本社会の方が、ウソに対してきびしいようですね。 ネット社会では、簡単にウソ情報が流れてしまうので、注意が必要ですね! |
|
| 相手があるから、自分もある! | ||
| 2022年 12月7日 (水) |
日本人は歴史好きですね。災害(自然災害や疫病災害など)が多く、歴史に学ぶ必然があったのでしょう。 しかし、現在は歴史に学ぶと言うより、外国に学ぶというスタイルになっています。 そのためか、人々のつながりが薄くなり、自然から学ぶことも少なくなってしまいました。 温暖化が問題となり、少しずつ自然への関心が出てきたようでが、むかしは、自然の中に神様が宿ると考え、自然を大切にしてきました。 また、核家族化が進み、昔のことを孫に引き継ぐことが難しくなっています。 子育ても核家族では難しいようです。母親一人で子育てをするには、チンパンジーは7年かけています。それまでは次の子供を産めないとのこと。 昔の日本の子育ては、両親と共に、おじいちゃん、おばあちゃん、近所の人達、みんなで育てることが、生物としての生き残り作戦だったようです。 それが、日本人が歴史好きになり、また、生き残りの作戦になったようです! |
|
| マニュアル通りやれば? | ||
| 2022年 12月3日 (土) |
今日(2022年12月3日)、相模原市にある有鹿神社の奥宮(おくみや) で、「有福玉清祓式」……お有鹿様からいただく新しい命を象徴する「有福玉」を奥宮の泉で清める「清祓式(きよはらえしき)」が斎行され、偶然、奥宮にいましたのでお声をかけていただき、参加させていただきました。 このような行事は、進め方に決まりごとがあり、その決まり事の通りに進めることで、神様から御加護をいただけると感じることが出来ます。 今流の言葉で言えばマニュアル化なのですが、なぜ神事と業務などのマニュアルは重みが違うのでしょうか? 偶然参加させていただいた神事なのですが、重みがまったく違うと感じることが不思議でした! |
|
| 赤飯の古いしきたり! | ||
| 2022年 11月21日 (月) |
お祝いの時に出される赤飯、これにも「物語り(しきたり)」があります。 伝統的なものには、「物語り」や「しきたり」があるものが多いですね。 「行事」や「その行事に使われるもの」、あるいは「お土産」などに物語があると、末永く続いていきますね。 古くからの商人の町には、伝説や民話などの物語が言い伝えられています。 やはり商売を長く続けるコツは、商品に物語を関連づけることなのでしょうね! |
|
| 旧暦八月十五日の「十五夜」! | ||
| 2022年 11月3日 (木) |
中秋の名月、2022年の十五夜は、9月10日でしたが、その1ヶ月後の「十三夜の月見」をした人はそれほどいないのでしょう。 十五夜の月見をし、十三夜の月見をしないと縁起が良くないのですが、今では気にする人はいないのでしょう。 ただ、いろいろな行事で自然観察をする機会は、多ければ多いほど、自然や歴史を知るには良いことですね。 やはり、多くの知識は、教科書より、体験が先にあった方が良いですね。自然環境の条件によっては、教科書が間違っていることもありますから! |
|
| 人間のもつ「108の煩悩」とは! | ||
| 2022年 6月16日 (木) |
日本では、宗教についてもある意味「曖昧」が許容されています。 多くの人は、あるときは神社へ、あるときはお寺に行きます。観光の時は、神社も、お寺も見て回ります。 この曖昧さが、思い込みの思想にとらわれることなく、たとえば、太平洋戦争後の世の中の変化が出来たのでしょう。 大乗仏教は、僧侶にならなくても涅槃の世界に行くことが出来ます。 僧侶にならなくても良いのです。 これも小乗仏教から見れば「曖昧」と見えることでしょう。 平安末期から始まった、お経を唱えれば極楽に行ける、という方法で、庶民の結団力が生まれ、それから庶民の力を評価する政治体制も、徐々に発達してきました。 一神教のように、宗教で人民を支配するのではなく、庶民を見据えながら政治を行う状況が、発展したり、衰退したりしながら、進歩してきたのでしょう! |
|
| 神社に参拝するとき! | ||
| 2021年 12月30日 (木) |
正月は神社にお参りすることが多いですね。 治承5年(1181年)に源頼朝が鶴岡若宮に参詣したことが初詣が広まるきっかけになったとの指摘もあるようです。 いつのころからか、生きている間の願い事は神社、亡くなってからはお寺にお世話になるとなっています。 お寺には、あらゆる病に効く薬が入った薬壺をもっている薬師如来、薬は生きている間に使うものです。 死んだあとに救済するのではなく、この世で利益を授ける如来として人気を集め、飛鳥時代には信仰が広まったのですが、新コロナが伝染している今、お参りに行く人はそれほど見かけません。 仏教は本来、生きている人を救っていたようですが、今はなんとなく、生きているときの願い事は神社になってしまったようです。 新年はやはり神社にお参りですね! |
|
| 冬至の日には、ユズ湯に入る! | ||
| 2021年 12月20日 (月) |
当時はユズ湯の日ですね。このような日は大事にしたいですね。 このような風土が健康に感心を持たせて入るのでしょう。 そういえば、神社に健康を祈ることも無意識にやっていますね。 それだけ「健康でいたい」という意識が高いのでしょう。 今回の新コロナの伝染を、ゆるやかにすることにも関係しているのでしょうね。 これからは、いろいろな行事が続いていく季節になってきます。 このような行事を大事にしていくことも、やはり安全な風土づくりに貢献しているのでしょうね。 大切にしましょう! |
|
| 古代中国の五行思想が雑煮にも! | ||
| 2021年 11月28日 (日) |
ハトは平和の象徴とされています。旧約聖書のノアの箱舟が由来だと考えられています。 しかし、伝書鳩は紀元前5千年とか、紀元前3千年のエジプトで通信手段として使われており、ローマ帝国では軍事用の通信手段として使われていました。 日本でも八幡神の使いはハトで、八幡神は源氏の氏神で武神です。 尾道の古いお寺には「源氏は伝書鳩を使うことが出来、平家は使えなかった」という言い伝えがあるそうです。 第二次世界大戦で日本軍のタイの通信部隊の人は、「無線はあったが、発電機は重く、山があると無線は届かない。伝書鳩の中には10日も同じ場所にいれば、その場所を覚えるので、軽くて大変有効な通信手段だった」と言っておられたそうです。 これらのことが関係しているのかわかりませんが、最近は平和の象徴としてのハトの出番が少なくなっていますね! |
|
| 古代中国の五行思想が雑煮にも! | ||
| 2021年 11月26日 (金) |
太平洋戦争の後、日本は焦土の中から立ち上がってきました。いままで、これは普通のことと思っていましたが、アフガニスタンの状況を見ると、国家という概念がつくれるのかどうかと考えてしまいます。 みんなで国づくりをするということはどうゆうことなのか? 戦後の日本人の多くは、どのような国をつくるかは曖昧だったような気がします。 思想的には曖昧なまま、とにかく生活(食べること)を中心にして、前に進んでいたようです。そして、少し食べることに余裕が出来ると、たとえば、畑になっていた庭をもとに戻していました。こんなやり方でまとまって行けた風土が、戦後の経済復興を成し遂げたのでしょう。 日本の風土に「思想では飯は食えない」ということがあり、ほとんどの人が、どんな思想も受け入れることができ、良い・悪いはどうでもよい、悪ければ直せば良い、そして、直すことが出来る、という風土の基本になっていたのでしょう。 思想で人をリードし、違反したら罪に問うという指導者がいた時代は、日本では争いが多く発生していた時代のようです。一人の個人が、時と場合により神も仏も信じる、そして、普段は神も仏も意識にない、という風土が、おだやかな国にする原点にあるのでしょうか! |
|
| 交通事故を起こした時のバイオリズムは! | ||
| 2021年 11月20日 (土) |
欧米には「バイオリズム」や「十三日の金曜日」というものがあります。 日本にも「七五三」や「七夕」、そして「石の上にも三年」「三度目の正直」「早起きは三文の得」」など数字に関係した言葉がたくさんありますね。 そのような区切りがあると気持ちの整理がつき、スッキリするという効果があるのでしょう。 「区切り…物事の切れ目」は、自分一人では切り替えられない気持ちを、世間の力をかりて、切り替える方法として生まれてきたのでしょう。 このような、ある意味「曖昧なしくみ」の多くを取り入れてきたのが日本の風土です。 日本では、この「曖昧さ」が許容されている時代は平和な時代でしたね。 現在の新コロナのときですら、日本は、ある意味政策は曖昧ですが、ほとんどの人は、守るべきことは守っています。 強権政策による反発と、曖昧政策の遵守度と、どちらが効果的なのか、答えは結果でしかわからないのでしょうね! |
|
| 初めての町で通りがかりの人に「こんにちは」! | ||
| 2021年 9月7日 (火) |
初めて行った町で、見知らぬ子供に「こんにちわ」と挨拶をされることがあります。 鎌倉では「まち案内のホームページ」作りで写真を撮っていたら、中学生の男の子に神社で声をかけられ、「約束した友達が来ないので、町を案内しますか?」と声をかけられ、二時間ほど案内をしてもらいました。 尾道でも、観光客があまり行かない坂道で、子供達に「こんにちわ」と声をかけられました。 こんな子供達に出会うと、その町がとても好きになりますね。 突然見知らぬ人に挨拶されると、最初はすぐにはこちらから返事ができなかったのですが、少し慣れたからは、挨拶をされたら、いつでも挨拶を返せるようになりました。 こんな町がどんどん増えてくるとよいのですが! |
|
| 大阪人は決してケチではありません! | ||
| 2021年 8月18日 (水) |
大阪人は、モノがもっている何かしらの役立つ性質や程度が、払うお金に対しての値打ちがあるのか、見分ける力が強いのでしょう。 ブランドや人気に左右されず、自分の価値観で判断する、ということなのでしょう。 自分達の価値観を持ち、それが定着したのは、江戸時代に江戸幕府の直轄だったため、幕府の指示に従いながら(従っているフリをしながら)、自分たちの価値観を造り上げたのでしょう。 テレビ番組の「水戸黄門」のように、印籠を見せれば、皆頭を下げひれ伏す、とはならなかったのでしょう。 「必殺仕置き人」のように、自分たちで解決していったのでしょうか。 当然、やりすぎて度が過ぎたこともあったのでしょう。 それが学びにつながり、風土として定着したのでしょうか! |
|
| 伝統的な「村八分」はいじめと違う! | ||
| 2021年 8月12日 (木) |
「村八分」という制度がありました。 村という集団の安全と平和を維持するために生まれたのでしょう。 いまも地域によっては目に見えない風土として、残っているところもあるようです。 現在流行している新コロナ伝染病の発生状況も、この風土と関係しているのでしょうか。 現代の日本では「個性」が大事にされていますが、ヒトの生存を考えたとき、個人と集団と、どちらを大事にするか、難問ですね! |
|
| 農耕が始まるまではたいてい空腹でした! | ||
| 2021年 7月21日 (水) |
米や麦の食べ方(料理)を見つけたのは、どこに棲んでいたヒトなのでしょうか? 料理というものは、ヒトの「口と消化器官を補助」するものです。米や麦の食べ方を見つけることができたので、安定的に食べられるようになりました。 しかも、それらは保存ができ、そのことで、より安定的に食物を手に入れることができるようになりました。 そして、農耕を知ることで、人はどんどん増えていったのでしょう。 ほとんどの動物は、せいぜい殻を割るくらいの料理しかできず、食べられる物の種類を増やすことができませんでした。 米や麦の料理方法を知ったことで、農耕文化が拡大したのですが、農耕文化は争いの文化も生み出してしまいましたね! |
|
| 「いただきます」「ごちそうさま」は誰に! | ||
| 2021年 6月9日 (水) |
天の恵み(太陽や雨)、地の惠(水)に感謝することは、ヒトが生き続けてくることができた原点にあります。 秘境に生きている人達には、それが今も残っているようです。 文明の惠を受けてきた人々は、やっと文明が必ずしも「恵ではないのでは?」と疑問を感じ始め、持続可能な開発目標(SDGs)が叫ばれるようになってきています。 しかし、秘境に生きている人達から見れば、まだまだ中途半端なのでしょう。 経済発展がヒト属が生き残っていくためのに良いのか、悪いのか、この判断が適正に行われるのか、難しい問題ですね。 多数決で決める民主主義社会では、なおさら難しいのでしょう! |
|
| お経は何かさっぱり分かりませんが! | ||
| 2021年 3月29日 (月) |
日本ではお経は漢字で書かれています。 そのためか、その意味を知ろうとします。 でも、分からないですよね。仏教の宗派によっては「文字で書かれていないところに真理がある」と考える宗派もあります。 生物として考えれば、その種が生き続けていく真理は、決して言葉ではない、と考えることが当然の真理です。 人間以外は生物は、言葉は持っていないのですから! |
|
| うるおいに満ちた精神性! | ||
| 2021年 3月17日 (水) |
日本の風土の基本に、「相手を思いやる」ということがあります。 災害が多く、大小の争いも西日本(琵琶湖周辺以西)では数多くあったためか、庶民か生き残っていくために「相手を思いやる」ことが大事になったのでしょう。 いくさでは、武士が農民たちから食料を略奪し、京都の昇ると織田信長のように、無理矢理に米を庶民に貸し付けて三割もの利息をとるなど、庶民たちはお互いに助け合わないと生き残れなかったのでしょう。 新コロナで緊急事態解除が首都圏で予定されています。 この地域の風土は、他の地域に比べて助け合いが弱く、能力主義で自己中心の人が集まっているため、再度コロナ蔓延の心配がありますね! |
|
| 体の毒を出して体を守るのが厄年! | ||
| 2021年 2月25日 (木) |
陰陽道は、「陽」と「陰」という視点から、バランスをとって物事を見ていこうともいえます。 思い込み・固定観念で物事を見ることの危険性を予知していたのですね。 「無」という考え方も、同じような考え方なのでしょう。 学問は、多くの「固定観念」を生み出してしまいます。 一神教も同じように「思い込み」を生み出しているのでしょう。 もしかしたら、AIも同じ道をたどる危険性があるのでしょうか? |
|
| 女性の井戸端会議は必要! | ||
| 2021年 2月13日 (土) |
生きていくため、食料の調達にほとんどの時間を使っていた時代から、井戸端会議は行われていたのでしょう。 飲み水の入手が難しい地域(夏の瀬戸内の川がない地域など)の井戸には石仏が置いてあるところがあります。 日常的に井戸には、近所の人達がほぼ同じ時間に集まるので、自然に情報交換の場になり、いやしの場になっていったのでしょう。 その頃は、男性たちは狩猟に出かけていたため、女性が水を汲むため井戸に集まっていたのでしょう。 狩猟のための情報交換と日常生活のための情報交換は、当然、話の内容も情報伝達のやり方も違っていたのが、現代まで伝わってきたのでしょうか? |
|
| 「縁起をかついでしまう」いいことですね! | ||
| 2021年 1月8日 (金) |
悪い出来事が社会に大きな影響を与えたとき、お参りするところ(神社)をつくり、神様を勧請し、お祀りをすることで、何とか乗り切って来た歴史があります。 このような行いをすることで、多くの人が社会のルールを守り、乗り越えることが出来たのでしょう。 昔からの商人の街では、「法律は最低のマナーだ、商人としてのマナーは、もっと上のマナーを身につけなければ……」というルールがありました。 法律より上のマナーが、長く商売が続くという幸運をもたらすことを大事にしていたのでしょう! |
|
| 運を変えたいなら視野を広げよ! | ||
| 2020年 12月9日 (水) |
日本の歴史は役400年ごとに激動の時期を迎えるとのこと。 戦国時代から400年後の激動、それは太平洋戦争で終わったと思っていました。 しかし、新コロナという疫病がはやり、まだ終わってはいないのでは、という気がしてきました。 世の中のしくみが、ここで大きく変わっていくのでしょうか? この社会に変化に対応できるのでしょうか? 現代は、知識教育が進み、教育では『答えは一つ」を教えています。 江戸時代までの「考えること」が中心だった教育から、「覚えること」が中心になっているいま、社会の変化について行くには、「指示待ち」だけでは発展は望めないのでしょう。 もういちど「考える」という教育が必要になってきているのでしょうね! |
|
| 日本の山村には森林が残りました! | ||
| 2020年 12月7日 (月) |
日本の自然条件はきびしく、工夫して生き抜いてきたようです。 西日本は台風の来襲があり、東日本は火山の噴火やその堆積物が多く、日本全体では、地震や津波があり、平野は洪水に見舞われることも多く、しかも、山岳地帯で移動がしにくい風土でした。 そこで、その土地に合わせて、工夫し、ルールをつくり、みんなで守り合うことで凌いできたのでしょう。 そのためか、ルールを守り、協力ができる遺伝子(不安を持ちやすい遺伝子)が多い人が、生き延びることができたのでしょう。 開拓心が強く、不安感をそれほと持たない人は、北海道の開拓をしたり、大都会で成功を目指したり、そのためか、伝染病には弱いのでしょうかと、ついつい考えてしまいます! |
|
| 龍安寺の石庭、コケの美学! | ||
| 2020年 7月18日 (土) |
コケが見直されているようです。 自然があれば、どこにでもあるような印象です。 昨今の外出自粛、コケの美学を追究してみることも一つの方法です。 コケは枯らした場合でも、罪悪感はそれほど感じなくても済ます。 石などにくっつけて、それをいろいろと配置し、楽しんでみたら如何でしょうか! |
|
| 神社に向かって手を合わし、心を整理! | ||
| 2020年 4月11日 (土) |
現代は、情報があふれ、接する人もあふれ、モノもあふれ、社会にはいろいろな出来事があふれています。 そのようなも雑多なものに合わせて行くと、どこかおかしくなってしまいます。 そのこころの掃除のために神社にいってみてはどうですか。神社が立地している地形を観察すると、災害に合わないような場所にあることが多いようです。 このような場所は、安全でパワーがある所なのでしょう! |
|
| 国によって違うジェスチャー! | ||
| 2020年 3月22日 (日) |
新型コロナウィルスがイタリアで大感染を引き起こしています。 イタリアは、家族が集まって食事をする事が多く、また、ジェスチャーを使ってのコミュニケーションも多い風土が原因に関わっているのでしょうか。 医療体制にも原因があるのでしょうが、もともとイタリアには1000年以上にわたって、ヨーロッパの医療技術の原点になっていたのですから、対策は難しいですね! |
|
| 手水舎で身を清める! | ||
| 2020年 3月20日 (金) |
疫病を鎮める神社が多くあります。 神社では、鳥居をくぐると手水舎の水で、手洗いと口をすすぎます。 現在流行しているウイルス対策として、推奨されていることと同じです。 昔の人は、現状把握とその対策、そして対策の定着化について、智慧を作り出していたのですね! |
|
| お辞儀で誠意を! | ||
| 2020年 3月18日 (水) |
「お辞儀」というコミュニケーションのやり方。伝染病の脅威に当面し、改めて工夫に工夫を重ねた結果つくり出されたやり方だと、先達たちの工夫の結実したものと思いました。 我々が何気なく行っている風習にも、多くの工夫が込められているのでしょう。 日本文化の熟成についてを、もっと気がつくことができれば良いのですが! |
|
| 中華文明は「核」を持たない文明! | ||
| 2020年 2月11日 (火) |
麦や稲は、耕作者の年間消費量の二倍の収穫ができた。 これが「戦い」の根本原因となった。 残った半分の収穫が、土地や農具の借賃、収穫した倉庫の護衛などに使われ出した。 農地の水の確保のため、大河の流域では巨大な開発事業となるため、大きな権力を持つリーダーが必要となった。 乾燥地帯ではより巨大な権力を持った皇帝が出現した。 日本でも、東日本は大きな河川があり、やはり、強権のリーダーたちが出現した。 地域の風土は、自然環境がつくりだすのですね! |
|
| 道端のお地蔵さんにはエネルギーが! | ||
| 2020年 2月1日 (土) |
道祖神は村の辻などに祀られて悪霊の侵入を防ぐ神様。 国際飛行場に道祖神を置いて、新型肺炎菌の侵入を防いでくれるとありがたいですね。 「固く信じる」ということは、宗教などで広く行われており、心だけでなく、からだにも何らかの効果があるのでしょうか? 医療がまだ発達していないとき、いろいろと信じることで、なにかしらの効果があったから、長い歴史の中で続けられているのでしょう。 「信じるという姿勢」こそが、未来を拓く大きな大きな力となってきた体験が、そうさせているのでしょうか! |
|
| 幽霊をみよう! | ||
| 2019年 12月19日 (木) |
それぞれの地域の風土に目を向け、歴史を眺めていくと面白いですね。 日本でも、東日本は組織の文化があり、西日本は庶民文化があります。 よく言われていたのは、テレビ番組にたとえ、東日本は「水戸黄門」、西日本は「必殺仕置人」が好まれるといわれていました。 水戸黄門が印籠をかざすと、印籠の権威でみんな言うことを聞いてくれます。 必殺仕置人は、庶民が仕置きを、庶民にお金で依頼します。 その背景には、歴史の積み重ねがありますね! |
|
| 聖徳太子の願掛けで勝利! | ||
| 2019年 10月28日 (月) |
仏教の伝来は、政治の権力闘争の材料でした。 仏教の教えが権力闘争に有効だったのか? 寺院や仏像が有効だったのか? どうも、寺院や仏像が有効のだったような気がします。 教えという抽象的な概念は、ある程度仏教が理解されていないと、有効にはならないでしょう。 しかし、寺院や仏像は見せ方で、有効な権力の象徴になります。 古びたお寺が修理され、朱色に塗り直されると、圧倒されるようになりますね! |
|
| ずっと着物で過ごしてみると! | ||
| 2019年 10月26日 (土) |
歴史を大切にすることが、安全と平和につながっているのでしょう。 着物の着方も中国がもとになっているのですが、中国の文化は政権が変わると、前政権の文化を全否定する文化なので、平和が長続きしないのでしょう。 ところで、「右前」とは、「右側を先にからだに着ける」ということなので、外側から見ると、左が前(上}になっているのですね! |
|
| 文字文化の伝達! | ||
| 2019年 9月22日 (日) |
文字の文化は、記録として残っているので研究されていますが、言葉の文化は、なかなかわからないようです。 また、言葉がなかった時代は、もっとわからないですね。 たとえば、毒キノコのように、毒のある食べ物の危険性を、どうやって伝えていたのか? DNAスイッチのOn/Offで伝わっていたのでしょうか? なんらかの伝達方法がないと、生き残ってはいけないでしょうから! |
|
| 源平の合戦に携帯(伝書鳩)が使われていた? | ||
| 2019年 9月2日 (月) |
日本の歴史の中で、通信手段として「伝書鳩」のことを語る歴史家は見かけない。 が、尾道の浄土寺の言い伝えでは、「源氏は伝書鳩を使っていたが、平家は使えなかった」と。 今でたとえると「携帯電話」に相当するのでしょう。 広島の原爆の一報は、原爆投下の少し後に広島を通りがかった新聞記者が、大阪の本社に伝書鳩で報告したとのこと。 何らかの事情で記事にはならなかったが、第二次世界大戦までは、ヨーロッパでも伝書鳩が使われていたという。 戦国時代の“いくさ”でも、伝書鳩が使われていたのでしょう。 江戸幕府が「伝書鳩を禁止」した事実があるのですから! |
|
| 外国にも「お盆」に似た文化がある! | ||
| 2019年 8月13日 (火) |
日本のお盆に相当する行事は、海外にもあるようです。 しかし、いろいろな文化をつくり出しながら、その多くを過去に置き去った国も多くあります。 日本は海外から入ってきた文化を、洗練しながら現在まで引き継いできているものが多くあります。 「文化は、現在に生きているからこそ文化である」と思います。 歴史は、単に記憶するものではなく、現在に生かすための歴史であってほしいものですね! |
|
| はじめて稲作が行なわれたのは! | ||
| 2019年 8月9日 (金) |
麦や稲の戦略は、ここ数千年の人類をうまく利用し、自分たち(麦や稲)の勢力拡大のためには、耕作者が消費する収穫量の2倍の収穫ができることができれば、自分たち(麦や稲)の拡大が可能だろうという戦力を見つけました。 耕作の残り半分が、農地の開拓者、農機具の所有者、盗難から警護する人達などに支払われ、また、それらの利益収奪競争が、人類の歴史を作ってきたのでしょう。 植物たちは、特定の昆虫や鳥や動物、自然現象などを巧みに利用し、生き残り作戦を行っています。 4億2千万年前には既に多様化した植物があったとのこと、今日まで、いろいろと生き残り戦略を行ってきたのでしょう! |
|
| 「花火」そのはかなさを! | ||
| 2019年 8月2日 (金) |
花火は、下から見上げるところが多かったのですが、高層住宅が増えてきたため、横から見る人も増えてきているのでしょう。 むかしは、海や川のそばに山があり、その傾斜地で各々が好きな場所を見つけ、花見見物をしていた所(たとえば広島県の尾道)もあります。 そんなところでは、高いところから少し下の花火を見る、といったところもありました! |
|
| かつての日本の家の中! | ||
| 2019年 7月27日 (土) |
実家に帰ると、”もの”があまりありません。 必要なものと、少しばかりの小さな置物類だけです。 しかし、家の外には豊かな(多彩な)自然があります。 部屋の中にものが増えるのは、都会生活で、まわりに心が安らぐ自然が少ないためでしょうか? |
|
| 完成形に至ると活力を失う! | ||
| 2019年 7月7日 (日) |
現在は、「完成形」を目指すことが当たり前になっている。 勉強、学術、工業製品、構築物、建物など、完全をめざす。 しかし、日本の文化には、「未完成の美学」というものがあり、あえて、完全なものを、一部を未完成にし、次なる進歩を追求する風土があった。 完全を目指すことは、誰もができるものではない。 できない者は、「おちこぼれ」として扱われる危険性がある。もっと、未完成・多様性を認める社会であって欲しい! |
|
| お経なんか、さっぱり分かりません! | ||
| 2019年 7月5日 (金) |
お寺さんと関わる機会が、ごく限られたときだけになってしまいました。 昨今、ストーカー、閉じこもり、いじめなど、心の問題が日常化しているとき、心を救うべく成立した宗教の教えや手法は、できが悪かったのか、あるいは、退化しているのでしょうか? これだけ多くの宗教施設がありながら、生きている人達を、もっと救うことはできないのでしょうか! |
|
| 日本人の未完成の美学! | ||
| 2019年 7月3日 (水) |
日本には、茶道具などに、ある意味未完成を尊ぶ文化があります。 また、浮世絵などに、後にいる人も、前にいる人も、同じ大きさに書くという、遠近法という論理では説明のつかないものがあります。 日光東照宮の「逆柱」、姫路城の天守閣にある「逆さ家紋」など、あえて完全というものを否定するものがあります。 たとえ、自分が日本一になったと思っても、「やっと三本の指に入ったよ!」といった言い方もします。 この発想にAIは対応できるのでしょうか? |
|
| 日本では、空気のような神々のあり方! | ||
| 2019年 6月5日 (水) |
日本の神様が生き残ったのはなぜでしょう? キリスト教などの論理的な宗教に、淘汰されなかった唯一の国、日本。知識と論理で成り立つAIにも、日本は何らかの競合策を生み出すことが出来るのでしょうか。 日本神様は基本は自然崇拝でした。「自然を大切にする」ということは、日本の自然は予測できないことが起きることがあり、そのため多少の余力を残しつつ、農作などを行ってきました。 この無意識に「余力を残す」ということは、論理的な考え方では組み込まれません。全力を出すことが良いこと、ということになります。 最近、身内の介護で「全力で介護はしないで、自分がつぶれてしまうよ!」と言われ出しました。また、引きこもりの原因は「全力を出せてない自分に、引け目を感じる」ということも、原因の一つなのでしょうか? 自然からの感性を得られないまま、知識教育だけで育つ危険もあるのでしょう! |
|
| 戦国時代の茶会! | ||
| 2019年 6月1日 (土) |
戦国時代、戦国のリーダー達の間に「わび茶」が浸透した。織田信長が茶器などを、褒美として武将に与えたことも理由の一つでしょう。 高価な茶器を褒美として貰った武将は、茶会を開き、貰った茶器を使い、自分のデモンストレーションを行うと同時に、ストレスの多い武将達の自律神経を安定させたのでしょう。 ただ、武将の部下達はどう思っていたのでしょう。 部下達はいくら手柄を上げても、「親分が茶器を貰って満足しているが、自分にはなんら収入アップがない」と、不満が蓄積していったことでしょう。 また、織田信長や豊臣秀吉を頼っても、部下達は「自分の収入アップは期待できない」と、感じていたことでしょう。「お金の切れ目が、縁の切れ目」ですね! |
|
| 古代の人々にとって鏡は神秘的なもの! | ||
| 2019年 5月30日 (木) |
このところ精神に異常があるのでは、と思われる凶悪事件が頻発します。 昔もあったのでしょうが、それなりのしくみがありました。 「わら人形を、丑三つ時に神社の森の木に釘で打ち付ける」、「呪いの祈祷をお寺に依頼する」など、精神面での気晴らしの方法がありました。 というより、神社やお寺が、生きている人をどう救うか、ということに真剣に取り組んでいました。 神社やお寺は、自分たちの存在価値をどのように考えているのでしょうか? |
|
| 相撲のはじまりは、642年! | ||
| 2019年 5月28日 (火) |
日本の伝統的なものは、すり足が多いようです。 格式を重んじるため、普段の歩き方と異なった歩き方を取り入れたのでしょう。 むかしの普通の歩き方は、道に迷わないため尾根道や坂道を歩くため、しかも、手入れの悪い道が多いため、腰(おしり)の筋肉で足を前後に動かし、太ももの筋肉で足を上下に動かしていたのでしょう。 しかし、現在は道が舗装されたため、多くの人がすり足で歩いているようです。 今でも少しですが、お尻の筋肉で足を前後に動かしている人も見かけます。 子供時代にクルマが通れない坂上で暮らしていたのでしょうか? |
|
| 分け合うという力が弱いと亡びる! | ||
| 2019年 5月2日 (木) |
食べ物に困ったときでも、「分け合う力(助け合う力)」が「生き残りの力」ですね。 しかし、日本の中でも助け合う風土は地域によって差があるようです。 四国のように、お遍路さんを受け入れる文化があるところは、「与えっぱなし」「貰いっぱなし」が当然で、ただ、ただ無心で与える風土が出来ているようです。 しかし、地域によっては「恩を与えたんだ」と、自己満足したい人が多い地域もあるようです! |
|
| 一神教や終末論は争いを激化する思想! | ||
| 2019年 4月12日 (金) |
宗教であれ、一神(一人)に権力や名誉が集中すると、不安定な社会になることが、人類の歴史で証明されています。 にもかかわらず、なぜ、そのしくみを改革できないのでしょうか。 人類史上、どの段階で権力・名誉・財力に特別な魅力を持つようになったのでしょうか。 やはり、農耕で麦を栽培するようになり、その麦が保存可能だったためなのでしょうか? |
|
| UFO、幽霊を信じますか? | ||
| 2019年 3月3日 (日) |
幽霊やUFOなど、不可思議なものに興味を持つのはなぜでしょう。 未知なものに出くわしたとき、生き残るための対応力を、身につけるための訓練の一つなのでしょうか? このようなとき、体内には何らかのホルモンが出て、からだは、日常と違う状態になる。 そのような状態を体験することで、本当に未知なものに出会ったとき、対応できるようになる、といったことでしょうか! |
|
| 神社の前を通りかかったら! | ||
| 2018年 12月31日 (月) |
鎌倉では神社の前を通るとき、立ち止まり、神社に向かってお辞儀をする人をよく見かけます。 外国の観光客が増え、外国人向けのお店が増えてきてはいますが、まだ日本の風土を守っている人もおられるようです。 日本風土を守っているが故、外国の人たちが観光に訪れるのでしょうか。 「観光」とは、見知らぬ土地に行って、何か役に立つことがないか、見つけることが目的だったようです! |
|
| 願いごとは、神様に誓うもの! | ||
| 2018年 12月19日 (水) |
神様にお参りして、願いごとをお願いする時期が近づいてきました。 でも、お参りは、お願いするのではなく、手を合わせて「頑張ります」と神様に誓うことなのですね。 来年は何をしようか、どう取り組むもうか、そろそろ考えを、まとめなければならないですね! |
|
| ある程度の自信があるが「変顔」 | ||
| 2018年 11月1日 (木) |
ネットに、自分の写真を載せる場面が増えています。 ある程度、自分に自信がないとできないですね。 その自信を「もっと増すことが出来るかな?」と、頑張っていますね。 そういった工夫の積み重ねが、いろいろな文化を生み出すのでしょう。 頑張りましょう! |
|