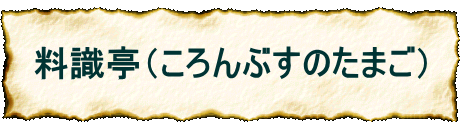| 好き嫌いと人間関係は別という風に区別! | ||
| 2025年 10月20日 (月) |
組織内において、好き嫌いという判断を基準にしてしまうと、組織の運営に支障をきたします。 あの人は「そうゆう性格なのか」で対応することが大事です。 好き嫌いは、個人的な付き合いの中だけで行うことが重要です。 仕事では、「好き嫌い」は除外してください! |
|
| 現在の家庭は“ボス”不在の社会! | ||
| 2025年 10月10日 (金) |
自民党の総裁選挙がありましたが、昨今はボス教育を子供時代に受けて人がほとんどいないので、とんでもないことをするリーダー(大統領、首相など)が出てきます。 これは民主主義の弱点のあるのでしょうが、社会そのものの問題なのかもしれませんね。 ほとんどの人々を大事にしなくても成り立つ社会を造り上げてしまったのでしょうか? |
|
| 権威者の指図とあればそれに従い、他人に責任転嫁させる! | ||
| 2025年 7月20日 (日) |
権威者に、人はどう反応するか、世の中で起きていることを見ると、想像ができます。 この権力者に対する反応の強弱は、風土によって違いがあるのでしょうか? それとも、政治体制によって違いがあるのでしょうか? 権力者によって違いがあるのでしょうか? ただ、現代では情報の操作による影響が強くなっているようです。 その情報も五感の内、「言葉」と「映像」に頼っているようです。 生成AIはこの分野の機能が発達しているようで、心配はありますね! |
|
| 最近の異常な犯罪は、子供時代の学びにあるのでしょうか? | ||
| 2025年 6月8日 (日) |
ガキ大将」という言葉が消えて数十年たちます。ガキ大将とは、子供時代に年齢の違う子供達が、一緒に遊んでいた頃のリーダー役の呼び名です。 ガキ大将は、小さな子供の体力を見ながら、どんな遊びを、どのようにして遊ぶか、同時に、年齢の違い子供が楽しく遊ぶにはどうするか、いろいろと工夫していました。 子供時代に、「縦社会のノウハウ」を身につけていたのです。 リーダーの役割だけでなく、小さな子供達も、リーダーという者の役割を学んでいました。 そのような学びの中で、社会での行動の仕方を身につけていました。 また、年齢の違う子供達の集団は、同学年での競争は、それほど気にすること無く遊んでいたので、不登校も無かったのでしょう! |
|
| 相手の目を意識して、過剰に気を使ってしまいまう! | ||
| 2025年 5月9日 (金) |
以前から、上司という立場になったら、気を使う必要が出てきます。 しかし、昨今は、この気づかいが拡大化し、管理職になることを嫌い、転職を考える人も出ているのでしょうね。 子供に時代に「ガキ大将」のしくみがなくなり、縦社会の基本を学ぶことなく大人になっています。 その大人が、上司という立場になると、部下も「ガキ大将」のしくみを学んでいないので、大変ですね! |
|
| 相手の目を意識して、過剰に気を使ってしまいまう! | ||
| 2025年 5月3日 (土) |
以前から、上司という立場になったら、気を使う必要が出てきます。 しかし、昨今は、この気づかいが拡大化し、管理職になることを嫌い、転職を考える人も出ているのでしょうね。 子供に時代に「ガキ大将」のしくみがなくなり、縦社会の基本を学ぶことなく大人になっています。 その大人が、上司という立場になると、部下も「ガキ大将」のしくみを学んでいないので、大変ですね! |
|
| 叱るときは、一つに的をしぼることが大切! | ||
| 2024年 12月22日 (日) |
しかるとき、その場でのことだけにすること、だそうです。 ついつい、記憶に残っていることも並べ立てて、しかっていませんか? 「しかる」は「育てる」こと。これに徹することが大切なようです。 そのためには、叱る側が冷静であること、これが前提条件ですね。 あと、しかる環境や叱る人の表情も大切ですね。 そのためか「顔色をうかがう」という言葉があるのでしょうか! |
|
| 物事をカイゼンする上での基本手法を「五つのWHY」! | ||
| 2024年 12月14日 (土) |
「ありかとう」と言うことは大切ですね。 「ありがとう」は、相手のために言う言葉です。 自己満足のためには言わないですね。 また、習慣的にも言うものではないですね。 「相手に感謝」すること、そのために「ありがとう」と言いましょう! |
|
| キャリアを積みたい人は、若いうちに転職したほうがいい! | ||
| 2024年 10月31日 (木) |
能力主義の社会になりました。スキルがないと安定した収入が得られません。 すると、どうしてもスペシャリストを目指してしまいます。 専門性は高まるのですが、思考の幅は狭くなってしまいます。 学校教育で、「記憶力」中心で脳を育ててきたため、もともと思考能力はそれほど育っていないようです。 そのような社会では、専門性を重視するスペシャリスト優先になって行くようです。 ただ、年を取り、退職すると、思考範囲が狭い人達は、どのようになっていくのでしょうか? |
|
| ガキ大将がいない今、縦社会のマネジメントを学べるか! | ||
| 2024年 10月17日 (水) |
今までは、神さま・仏さまの「願い事」をしていましたが、これからの願い事は「生成AI」になってしまうのでしょうか? 「神頼み」は、実現しなくても、「しょうがない、自分の責任だ!」で済ますことが出来ますが、生成AIでは、どのようになるのでしょうか? 生成AIでも、自分の責任と考えることが出来るのでしょうか、異常な犯罪が増えている現在、心配ですね! |
|
| 避けて通れぬことは避け無い! | ||
| 2024年 9月7日 (土) |
動画や文字情報は、“見ている”という意識がありますが、色については、見ているという意識はそれほどありません。 しかし、気持ちや心への影響はかなりあるようです。 商店など、人を引き込む所では、かなり意識されているようです。 人は、意識していなくても、色は、人の行動を左右しているようです。 色彩の認知度は、男女差があるのでしょうか? もっと注意して、色彩の影響を意識しなければ行けませんね! |
|
| パワーハラスメントへの対応は? | ||
| 2024年 8月2日 (金) |
パワハラ(パワー・ハラスメント)は、脳の構造に原点があるようです。 基本的には、男女の脳の構造に違いがあり(もちろん女性でも、男性脳に近い人もいれば、その逆もありますが)、男性脳に多いようです。 ということは、相手の「脳の構造を直す」ことはできないので、こちら側の対応を変えるか、社会的な対策をするしかないのでしょう。 まず、しょうがないので、こちら側の対応を工夫してみましょう! |
|
| ピラミッド型の組織を維持して行くには、失点主義! | ||
| 2024年 6月13日 (木) |
日本では失点主義が横行した反面、そのおかげで、人の過ちや人間的弱さというようなものを、許し合う仲間を作って救い合ってきた。 年功序列の制度も、そのような面があった。 しかし、競争社会は許し合うことがなくなり、むしろ失敗捜し、時には、失敗を捏造する社会になりつつある面も垣間見える。 SMSで人を中傷する情報も生まれつつある。 今日社会の弱点を知った上で、どのような組織にするか、難しい時代になってきています。 日本の歴史風土を生かし、乗り越えたいものです! |
|
| 腹が立つ感情を捨てる! | ||
| 2024年 5月10日 (金) |
「腹の虫」という言葉は今でも使われています。昔は病気の原因を「虫」といっていました。 たとえば庚申信仰。悪いことをしたかどうか監視する虫が、人の中に住んでいました。その虫が60日に一度、夜寝ると、天の神様に報告に行きます。 その報告をさせないため、その夜はみんなで集まり徹夜をします。 それが庚申塔があるところで行ったそうです。 きっと酒を飲み明かしたのでしょう。 ところで、「虫歯」という言葉は、まだ虫が残っていますね! |
|
| 社会に出ると完全な縦社会! | ||
| 2023年 12月4日 (月) |
社会に出ると、学生時代の横社会から、縦社会に変わります。しかし、この縦社会は、昔の縦社会とは違っています。 現在の縦社会は、下の者が、上のご機嫌を伺う、というスタイルです。しかし、昔の縦社会は、リーダーが、下の者の能力や性格を考え、その人が一番能力を発揮しやすい環境に、置くことを考えていました。 ソ連の捕虜になった、第二次世界大戦の日本兵捕虜の班長ですら、班員の性格や能力を見極め、配置していました。 これは、子供時代に、ガキ大将を中心に、年齢が10歳以上離れた子供達が、一緒に遊んでいので、ガキ大将は、下の子供達の能力を考えながら、安全を確保しながら、みんなでいかに楽しむかを、考えながら遊んでいました。 例えば、ソフトボールで遊ぶとき、中学生がピッチャーで、小学3年生がバッターの時、力一杯投げますが? 手加減して投げることを学んでいました。 しかし、そのような体験がある世代は、昭和15年(1940年)生まれ位まででしょうか! |
|
| 子ども時代にタテ社会の中で生きる体験! | ||
| 2023年 11月12日 (日) |
「ガキ大将」というものが、過去のものになってしまいました。 子供時代、年齢の違う子供達が、それぞれの年齢と能力を考えながら、教え・学ぶ体験を失ってしまったようです。 自然の中で、年上の子は、下の子の能力を考え、年下の子は年上の子に学び、安全で、楽しく遊ぶ経験は、大人になっても大切なものです。 特に組織の中では、周りの人たちの能力や性格を見極め、それぞれの人に応じた対応が必要です。 それが、組織全体の能力につながっていきます。 「ガキ大将」が復活するとよいのですが! |
|
| 自分のホンネをさらけ出すのは危険な場合も! | ||
| 2023年 11月4日 (土) |
パワーハラスメントが、ニュースで取り上げられる事が多くなっています。 事実をきちんと把握して話しができるのか、気分で話すのか、でも違ってきます。 1980年頃から製造業に広まっていった「トヨタの小集団活動」の方式。 この方式では、「現状把握」に活動時間の9割以上の時間をかけていました。 もれなく現状を把握することを、活動の重要事項としていました。 現状の把握が出来れば、対策は自然に思いつくもの。 コミュニケーションにおいても、まず、事実・現状把握を伝え、それをもとにして話しをしていくと、良い結果が得られるのではないのでしょうか! |
|
| 権力を握ったままなかなか引退しない | ||
| 2023年 10月23日 (月) |
「能力主義」が叫ばれています。若くしてトップになった人は、どのタイミングで引退すればよいのでしょうか? 人間の性(さが)として、「権力・財力・名誉」にはしがみついていたいもの。 その地位から下りることが出来るでしょうか? その弊害から逃れようとして、年功序列が生まれたのでしょうか? 組織において、これで万全といった制度はなかなか難しいですね。 参考になるとしたら、江戸幕府の体制でしょうか? |
|
| 思い通りに部下が動くことなど期待しないこと! | ||
| 2023年 10月17日 (火) |
部下を「自分の思い通り動かす」を基本としている上司は多いようです。 その場合、「組織の思い」「世間の思い」をどれほど意識しているかによって、部下の動きは違ってきます。 「自分の思い」の正当性を常に吟味し、指示を出したいもの。 ただし、人を自分の思い通り動かす、という発想そのものが、難しいことを認識し、相手に社会における正当性を、きちんを伝え、相手が自発的に動くようにさせることが、基本中の基本なのでしょう! |
|
| 上司も部下は、単なる役割分担! | ||
| 2023年 9月9日 (土) |
日本にも、能力主義が叫ばれ、取り入れた企業もある時代。 ただ心配なのは、若くしてリーダーになった人が、長期間その地位にいると、組織の流動性が阻害されるのではないか? という心配です。 若ければ若いほど、その権力・地位・収入にこだわる危険性があるからです。 江戸時代のように、権力や財力、名誉が分散されるしくみがあれば、ある程度はその危険から遠ざかることも考えられるのですが、そうでなければ、危険なリーダーが、長く支配することも起きてしまいますね! |
|
| 叱った後は、叱り終わった合図を! | ||
| 2023年 5月28日 (日) |
「叱る」とき、「叱り終わり」を考えてから叱っていますか? 叱る目的は、叱る相手に何かしらの改善を要求し、そして、結果を出してほしいから叱っています。 叱った結果は、どの程度改善が実現していますか? よく見かけるのは、叱る側のストレス解消のため叱っている、と感じてしまうことがあります。 これでは、叱られた側もストレスが残り、双方とも何のメリットも生まれてきません。 何かしらの改善が生まれる叱り方を、充分考えてから、叱りたいですね! |
|
| 「のに病」から解放し、意気揚々と! | ||
| 2023年 4月20日 (木) |
「進め 進めと 上司逃げ」、「出る杭を 叩いて上司 上を見る」、「聞かれたら ウマクヤレヨの 言葉のみ」。 人生、組織での暮らし方を身につけないと。 これは、社会での暮らし方と同じですね。 これを身につけないと、異常な犯罪に手を染めるキッカケにもなります。 ヒトが生存し、人口を増やすことが出来たのは、「社会」という人のつながりをつくり、自分というものに、ガマンを覚えさせ、協力することができるようになったのではないのでしょうか。 ネアンデルタール人より脳が小さいホモサピエンスが生き残れたのは、ネアンデルタール人より大きな集団をつくり、その中での暮らしが出来たからでし |
|
| 頭が固くなってしまうとボケやすい! | ||
| 2023年 4月14日 (水) |
50才から60才にかけて、自分の興味を広げる対策を立てることが、定年後の充実した人生を送ることにつながるようです。 この時期に責任のある地位にいると、なかなか自分の興味を広げることが難しくなります。 年功序列を改め、能力主義になると、この問題は解決する可能性があるのでしょう。 江戸時代に当てはめてみると、権限のある人は老中(石高が少ない)=能力のある人(しかし、収入はそれほど高くない人ということに)、収入のある人は外様大名(石高が高い)=年齢の高い人(収入が多い、しかし、権限はそれほどはない)、という年功方式であれば、歳をとっても、新しいことに興味を持ち、元気な高齢者が増え、定年後に社会に貢献できる余地も出てくる可能性が、広がってくる可能性があると思うのですが。 また、子どもにも充実した教育環境を整えられるのでは、難しいですかね! |
|
| 無欲になれなくても、小さな欲望に! | ||
| 2023年 4月4日 (火) |
人が求めるものの原点に、お金・権力・名誉・寿命がありますが、現代は多くの方が「お金」なのでしょうか。 そのためか「能力主義」が叫ばれています。 しかし、年功序列の時代は、先輩が後輩をよく指導していましたが、能力主義になると、先輩の指導はあまり期待できなくなります。 自分で能力を高めていくしかなくなってしまいます。 日本では、高度成長が出来た時代は、年功序列の時代でした。能力主義になると、日本全体では、どの程度の成長が期待できるのでしょうか。 今回のワールド・ベースボール・クラシックでの日本の活躍は、日本の年功序列時代の組織を思い出してしまいました。 先輩が熱心に後輩に教えていました! |
|
| 外面がよく見えてても中身ブスなら! | ||
| 2023年 3月5日 (日) |
地位が上がれば、収入・名誉も上昇、尊敬されるという世の中。この方式を打ち破っていたのが徳川家康。 収入の多い10万石以上は外様大名、幕府の重要な地位には就くことが出来なかった。老中になれる大名は、数万石の譜代大名。 また、名誉は「武士は食わねど高楊枝」という言葉があるように、江戸時代の武士は、下の者でも名誉をめちゃくちゃ大事に考えており、その反対に恥をひどく嫌いました。 上位のものに、権力・財力・名誉が集中することの危うさを、完全に避けるシステムを作り上げることで、安定して時代を造り上げたのでしょう。 独裁国家を否定することで、平和な社会をつくりあげることに成功したのでしょうね! |
|
| 全員一致は本来はあり得ないこと! | ||
| 2023年 2月19日 (日) |
日本は「根回し」文化の国です。根回しには談合もあります。『日本書紀』の時代から談合の国です。 A建設、B建設、C建設などさまざまな企業が談合で出てきます。 そういった取捨選択、あるいは格付において絶妙に配慮が行き届いて、忖度しているといった具合です。 だから、『日本書紀』は日本の忖度文化の原型ではないかと思います。 いわゆる独裁的な王権があったのではなく、連合王権のような国として成立してきました。 「根回し」には悪い面もありましが、良い面もあります。 それは独裁者が出てこないことです。日本の独裁者と言える人物は織田信長ぐらいでしょう。 根回しの段階で、部下の意見を取り込むことができます。また、部下を上司の意見に近づけることも出来ます。 独裁国家にならないためには、効率に問題はあるのでしょうが、「根回し文化」もあって良いのでは、と思いますが! |
|
| マニュアル通りやれば? | ||
| 2022年 12月3日 (土) |
今日(2022年12月3日)、相模原市にある有鹿神社の奥宮(おくみや) で、「有福玉清祓式」……お有鹿様からいただく新しい命を象徴する「有福玉」を奥宮の泉で清める「清祓式(きよはらえしき)」が斎行され、偶然、奥宮にいましたのでお声をかけていただき、参加させていただきました。 このような行事は、進め方に決まりごとがあり、その決まり事の通りに進めることで、神様から御加護をいただけると感じることが出来ます。 今流の言葉で言えばマニュアル化なのですが、なぜ神事と業務などのマニュアルは重みが違うのでしょうか? 偶然参加させていただいた神事なのですが、重みがまったく違うと感じることが不思議でした! |
|
| 労働力が重要なのは生かされている場合! | ||
| 2022年 12月1日 (木) |
むかしの縄文時代の土器は、手の込んだつくりをしています。 これを、仕事としてとらえると、大変だなと思います。 しかし、趣味という視点でとらえると、まあまあという評価になります。 出来上がったものを、仕事という視点でとらえるか、趣味という視点でとらえるかで、出来上がったものの評価が分かれることもあります。 縄文土器については、専門家の人達は、仕事という視点で捉えているようですね! |
|
| 学習性の無気力を払いのける! | ||
| 2022年 11月23日 (水) |
昔の職人のように、技術を「見て盗む」という機能が劣化してきているようです。 これは、教科書やマニュアルで学ぶというやり方が影響しているのでしょうか。 また、子供時代に、自然の中で子供達だけで遊ぶ経験がなくなったためでしょうか。 それに加え、ナット社会になり、実際に相手の表情やしぐさを見る機会が少なくなった為でしょうか。 生物としてのヒト族の能力が、落ちてきているようですね! |
|
| 本当にいじわるな人は間接的にいじわるを! | ||
| 2022年 11月15日 (火) |
意地悪な人が増えているのでしょうか。異常な行動をする人が増えているのでしょうか。 子供時代から、「答えの正解は1つ」という環境で、教育や躾けられた環境で育ってしまうと、考え方が非常に狭くなってしまうのでしょうか? 学者もスペシャリストも、狭い分野を追求した方が、社会の評価が上がるしくみになっているためか、考え方を狭くすることが奨励されていると、受け取ってしまうのでしょうか! |
|
| ピラミッド型組織がやがてだめになる! | ||
| 2022年 10月30日 (日) |
リーダー的指向を目指す人は、ピラミッド型組織で権威を手に入れようとする傾向があるようです。 これは、権力・財力(お金)・名誉を、全てリーダー1人に集中する思考です。 歴史を見ると、これらを1人に集中すると不安定になる、という反省からか、江戸時代は、権力・財力・名誉の三つを分割しています。その結果か、文化が栄え、文字を読める人も増え、浮世絵などの芸術を庶民が楽しめる時代になりました。 ロシアや中国のビラミッド型社会を見ていると、自由な風土とは、ほど遠いようですね! |
|
| 従業員についてきてもらうためには! | ||
| 2022年 10月28日 (金) |
ロシアや中国のニュースを見ていると、「リーダーシップとは?」という疑問が湧いてきます。 リーダーが「求心力が落ちてきた」と感じた瞬間から、非常に危ない方向に行ってしまいます。 それを止めるには、反対派が勢力を持ち、そのリーダーの拘束か、死を待つしか無いのでしょうか。 日本のように、ある程度の「曖昧さ」・「いい加減さ」がある風土では、強権を発することがなく、平和を維持できるのでしょう。 曖昧さを持つことで、部下の意見を聞くことが出来、いろいろな提案を検討できる余地もできるのでしょう。 オイルショックの際に、製造業に広がったトヨタ式現場改善活動も、地位に関係なく、どんな人の提案も、否定することなく、どんどん改善提案を出させたことで、オイルショックの危機を乗り切りましたね! |
|
| 仕事は一人で行うものではありません! | ||
| 2022年 10月24日 (月) |
忙しいと、やはり周りが見えなくなりますね。それが永く続くと、自己中心になってしまいます。 このようになってしまったときは、昔の歴史や風土が残っている町を、のんびりと歩いてみたいものです。 そして、その風土を感じ取れるようになるまで、のんびりと繰り返していると、いつの間にか心にゆとりを取り戻してきます。 そのためでしょうか、昭和を感じられるところに、人が集まっているようですね! |
|
| <自分>という製品を売る! | ||
| 2022年 10月6日 (木) |
いかに「自分という商品」を売れるようにするか。これが今の社会で最重点が置かれています。 年功序列の時代は、会社が社員を教育・訓練し、社員を有能化していました。 しかし、能力主義の時代になると、自分の商品化は自己責任です。 しかも、時が経過しても、商品としての自分を劣化しないようにする責任も自分にあります。 自己責任が強調されると、周りからの支援も少なくなりがちです。 ますます自己責任ということになりますね! |
|
| 組織とのつきあい方は工夫が必要! | ||
| 2022年 9月22日 (木) |
実力や実績が重視される世の中、その結果、スペシャリスト指向が強くなっています。 そのためか、能力な範囲が深くはなるのですが、どんどん狭くなっています。 異なる視点からものごとを見ることができないため、世の中が変化しているときは、その変化に対応できません。 変化に対応できない、という生き方は、仕事を失ったとき、あるいは、リタイヤしたとき、その後の人生の幅を広げることが出来ないまま過ごすことになります。 長寿社会の現在、なんとか工夫をしなければならないですね! |
|
| 好きなことを知ってはじめて仕事は回る! | ||
| 2022年 9月16日 (金) |
仕事の処理が得意な分野と、その人が好きな分野は必ずしも一致しません。 好きなことは、時間がたつのを忘れて取り組んでしまうため、必ずしも効率的とは言い切れません。 しかし、好きな分野は、どんなに困難があろうとも、なんとか乗り越えようと取り組んで行くことができます。 時代が変化しているときは、好きなことに取り組むべきなのでしょう! |
|
| 役割を誇示すること! | ||
| 2022年 8月29日 (月) |
オイルショックの頃、トヨタの「小集団活動」が製造業に広がりました。 この活動は、「現状をありのまま」に把握する。 それも出来るだけ数値化する(数値化で、より先入観を排除する)。 しかも、現状把握に活動時間の9割以上を費やす。 そして、改善策を検討するときは、役職に関係なく、どんな意見もリストアップする。 他人の意見に分乗してのアイディア出しもOK。 改善案が出た後は、それぞれの案を比較評価し、全員で個別の案を比較し採点する。 その中から上位の2~3の案の具体化を検討しテストする、といった手法でした。 それが製造業に普及し、高度成長の源になっていったのでしょう! |
|
| アメとムチの使い分けに工夫を! | ||
| 2022年 6月24日 (金) |
上司が部下を使うとき、どのようにすべきか意識していますか? パワーハラスメントのニュースがよく流れます。 上司の方も気を使う時代です。どの程度が良いのか、難しいですね。 日本の教育は、答えが一つしかない教育を受けています。 そのため、一つの言葉に、いろいろな意味が含まれていることをあまり考えません。 ある意味、単純な解釈しかしないこともあります。 愛情が隠されているきびしい言葉は、表面のきびしさだけで受け取ってしまうこともあります。 難しいですね! |
|
| 周りの人から嫌われる傾向の人! | ||
| 2022年 2月14日 (月) |
社会には、一人でする仕事と、複数の人でする仕事があります。 画家や作家、伝統工芸の職人など、一人で完結する仕事では、市場を意識した上で、個人の能力発揮だけでも、それほど問題はありません。 しかし、そのスタイルで組織の中で仕事をしてしまうと、浮き上がってしまいます。 スポーツでも、個人競技と団体競技があります。 団体競技で能力がある選手は、まわりの選手の個人個人の特性を把握し合い、お互いにそれぞれの選手の能力を生かす方法を選択します。 強いチームを見ていると、ときどき笑顔を見ることがあります。 チーム(グループ)で活動するとき、笑顔がそのチームの能力を引き出す秘訣のようですね! |
|
| ねぎらいのコトバをかけたいもの! | ||
| 2021年 9月29日 (水) |
どんなとき、どんなところでも「、どうもありがとう」は言いたいですね。 ちょっと気に障ったときでも「ありがとう」と言えば、自分の気持ちが収まりますね。 このような習慣が身につくと、自分の思い込みもゆるやかになり、自然に「どうもありがとう」と言えるようになります。 忙しい中にいるとなかなか難しいのですが、これも「慣れ」です。 日ごろから練習しておきましょう。 |
|
| 怒りが静まる時、後悔がやってくる! | ||
| 2021年 9月17日 (金) |
肩書きに関係なく、リーダー的な先輩がいると、後輩はどんどん育っていきます。 そのような先輩は、肩書きなどにこだわることはありません。 現状の把握をもれなく正確に行った上で、自分の知識に固執せず、いろいろな知識や意見を集め、判断をして行きます。 そのような行動を見た後輩は、結果的に間違った判断であったとしても、先輩を見習うようになり、どんどん間違いが少なくなっていきます。 自分の肩書きにとらわれ、自分の思い込みに固執した判断で、結果が思わしくない状態が続くと、下の者はつらいものです! |
|
| 目は口ほどにものをいう! | ||
| 2021年 9月15日 (水) |
「ボス」と「リーダー」をどのように使い分けていますか。 日本語では、ボスは『親分、親方』、リーダーは『指導者、統率者』ですが、昔の親分(ボス)は、「面倒見がよく、親のように頼りになる人」と思われていました。 ヤクザの元親分が県会議員になっていたりしていた例もありました。 現在の暴力団の親分は「部下に対して恐怖を与えて従わせようとする」ように思われています。 どちらかというと「ニホンザルのボス」のようです。 リーダーと言われる人は「部下のやる気を引き出させて任務を遂行させる人」と思われています。 「ゴリラのトップはではリーダー」のようです。 昔のヤクザのトップのような「面倒見の良い親分」が育たなくなりましたね。 やはり、子供のときの「ガキ大将」がいなくなったことが原因なのでしょうね! |
|
| 何かしらモノに触れてストレスを緩和! | ||
| 2021年 9月9日 (木) |
雑用が溜まってしまうとストレスになりますね。 手をつければ「思っていたより早く終わってしまう」ことも多いのですが、なかなか手がつけられません。 また、慌ててやってしまうとミスが起きてしまいます。せめて仕事だけは、大雑把ではなくまめに取り組みたいものですね。 それがなかなかできないので、トヨタのように「小集団活動」で、現状把握をもれなく完全にやることで、現場改善の活動がうまくいったのでしょうね! |
|
| こころの奥に残っている痛みは……! | ||
| 2021年 6月25日 (金) |
自慢話には「ふうん」「あ、そなんだ……」でよいのですが、陰口を聞かされるときには、陰口に同調しないことが大事なようです。 もし、相手にノセられてうっかり悪口を言ってしまったら、「でも考えすぎかな」「自分の勘違いかもしれません」とすぐにフォローの言葉を添えること。 また、その場を離れることも考え必要があるようです。 陰口の背景には、子供時代の育てられ方に原因があるようだ、と言われています。 もし悪ロ・陰ロを言ってしまったら、間を置かず、手帳などに相手の良いところを書くようにすることが大切とも言われていますが、ここまで大人の対応ができる人は、陰口などは言わないのでしょうね! |
|
| 論理が重要なのか、感情が重要なのか! | ||
| 2021年 6月13日 (日) |
自然淘汰の法則の「弱いものが消えてゆく」というものですが、この解釈が「自然の中での出来事」ではなく、「社会の中での出来事」として解釈する人が多くなっています。 ヒトの場合、食料を運ぶことが大変だった時代は、秘境や小さな島では、その土地で生産が可能な量で生活が可能な人数しか生きていけません。 その中で、生物としての本能に基づく自然淘汰のしくみが必要でした。日本でも、「口減らし(人数を減らすこと。特に,子供を奉公に出したりして,生計の負担を減らすこと)」や「間引き」というしくみがありました。また、団塊の世代の就職時期から言われ出した「集団就職」なども、ある意味では口減らしなのでしょう。 自然淘汰の法則は、社会現象との関わりが深いため、「社会の中での出来事」と思われるようになったのでしょう。 ただ、新コロナの蔓延対策は、「社会の中での出来事」という発想では「民主主義国家で強い人=投票に行く人」中心ではなく、「自然の中での出来事」という視点で、新コロナ蔓延地区の人、その地域に出入りする人」のワクチン接種を優先する対策をしてほしいものです! |
|
| 上司が部下を信頼して権限を! | ||
| 2021年 6月1日 (火) |
社会においては、多くの人達は仲間よりは上の者(組織では上司)を重視します。多くは利害関係が関係しているようです。もちろん尊敬できる上司の場合もあるのでしょう。 農耕社会がはじまって、一家が必要とする食料以上に収穫できるようになると、物々交換がはじまりました。そして、より生産性を上げるため栽培技術が上手な人の言うことを聞くことがメリットを生むため、その人に従うようになりました。 軍も、戦いが強い人に従えばメリットが大きいため、その人に従うようになりました。 自給自足ができる地域では、経済がそれほど発達していないため、生物本来の姿である「子孫を残す」ということが第一優先です。そのため、生きることの経験が豊富なお年寄りの言うことに従うようです。 地球環境が大きく変わったとき、自然条件が厳しいところで自給自足をしている人達が、ヒトの生き残りに有利な時代がくるのでしょうか? |
|
| 専門家と呼ばれる人はそこでしか生きられない人! | ||
| 2021年 4月12日 (月) |
「定住を基本とした社会」か、「移動を基本とした社会か」で、その地域の風土がかなり異なるようです。 移動を基本としている社会は「能力主義」が基本になります。 しかし、定住を基本とする社会では、個々人の能力が平準化した方が、その社会がより協力的になり、不満も少なくなると思います。 現在の日本は、欧米の考え方の比重が高くなっており、能力主義がよいとされているようです。 しかし、日本では「少しばかりの能力の差」が、過大に評価されないように注意する必要があるのでしょう! |
|
| 「つまらない話ばかりして」! | ||
| 2021年 2月11日 (木) |
会議が時間オーバーすることは、ビジネス関係ではまずないと思います。 出席者のほとんどは、予定を立てており、会議で予定された時間内で終わらせないと支障が出るためです。 子どものときから学校の授業で、時間割をしてその時間内で終わらせる授業を受けており、企業に就職してからも、会議に出る立場になる頃までには、時間を守ることが習慣になっています。 井戸端会議的な雑談の場でも、終了の時間は意識しています。 その習慣が身についていない人もきっといるのでしょう。日本の事務効率が悪いと、他の国の人達から言われているのですから! |
|
| 能力主義には限界がある! | ||
| 2020年 11月27日 (金) |
いまは能力主義の社会になっています。 この能力というのは「お金」に関わる能力のことで、それ以外の能力は、それほど社会では認められません。 戦国時代の能力は「いくさに関する能力」が評価されていました。 そうした能力主義の時代は、自分が生きている時代中心のことしか考えません。 子孫代々の繁栄は二の次です。そのためか、織田信長や豊臣秀吉は、実質一代のみです。 そうゆう社会の弱さに気がつき、多方面の能力を社会に生かす時代ができたのが江戸時代です。 社会に幸せをもたらすことは、お金による豊かさだけではないのでしょう。 もっと多彩な能力が必要なのでしょう! |
|
| 人は誰でもが出来損いである! | ||
| 2020年 11月11日 (水) |
中国の主君に対する格言で、一番良い主君は、人民から見て「主君が、いるのか、いないのか、分からない社会が一番良い」とされています。 庶民が自由に生活しながら秩序が保たれ、安定した社会が理想の社会ということです。 その風土か現在でも何とか残っているのは、日本だけになっているのでしょうか。 今でもたくさんの神々がおり、仏教があり、いろいろな宗教もそれほで否定しない風土があるのも珍しい国です。 ただ、外国の情報が大量に流れ込み、英語教育も強化される社会、強いリーダーが良いとする社会に移っていくのでしょうか? 生物としての人間は「子孫に繁栄を引き継いでいくこと」が大切とされています。 織田信長も豊臣秀吉も、子孫に繁栄を残していません。しかし、現代では、すごい英雄と考えられていますね! |
|
| ミスを報告してくれたことを評価する! | ||
| 2020年 11月9日 (月) |
いまはミスに厳しい社会になっていますね。 その基本にあるのは、損害賠償の判決で、賠償金が入るようになったからなのでしょうか? クレーマー社会のためなのでしょうか? ミスに厳しい社会のため、専門家を目指す人が増えいるようです。 専門家は自分の分野だけやっているので、ミスが少なくてすみます。 しかしミスをした場合は、ミスに対して厳しいですね。 しかし視野が狭いため、専門領域以外は口を出さないですね。 もっとミスに対して、優しい社会になって欲しいですね! |
|
| ただ単に大声で訴えても! | ||
| 2020年 8月17日 (月) |
「大声」で話すときは、おそらく自分に自信がないときなのでしょうか? もちろん、多くの人に伝えるときには大声を出します。 しかし、2~3人程度のときに大声を出すのは、「威圧」しようと思っていることが多いのでしょう。 筋の通った説明ができないため、しかし、なんとかやらせたいため、大声になりやすいのでしょう! |
|
| 会社から飛び出して何ができるか! | ||
| 2020年 8月9日 (日) |
親の言うこと、先生の言うこと、上司の言うこと、などを聞く(従う)ように育ってくると、現在の新型コロナウイルス対策においても、政府の言うこと、知事の言うことなどに従おうとして、ハッキリした指示がでないと不満を漏らします。 テレビに出てくる評論家達の多くも、「国からハッキリした指示が出ない」とこぼしています。 世の中には「指示待ち人間」が明らかに多くなってきているようです。 高度な教育を受けるほど、他人(指導者・専門家)の知識で判断・行動するようになるのでしょうか? ハッキリしたことが分からないときには、自分の「体験や経験」で推測し、判断するしかないのですが、指示待ちになる人が多いようです! |
|
| 人をイラつかせる人がいる! | ||
| 2020年 5月27日 (水) |
人をイラつかせる人がいます。 が、以前は顔が見えていました。 しかし、SNSの時代になり、顔も名前も見えなくなりました。 その結果、過激な情報発信でありながら、社会からの、発信者に対する避難もできなくなり、情報発信者は自制もなく、社会からの非難も届かず、ますます過激になりました。 むかしは、「村八分」という制度があり、「火災」と「葬式」以外のつきあいを断絶していました。 そのおかげで災害の多い日本で、集団として生き残ってきたのでしょう。 なんらかの新しいしくみが必要なのでしょう! |
|
| 相手の話をじっくり聴こう! | ||
| 2020年 5月13日 (水) |
余裕のない時間の過ごし方に馴染んでしまったためか、新ウイルスで自宅待機がつづくと、戸惑ってしまう人が多いようです。 家の中の片付けや、季節の移り変わりで衣類の片付けも良いのですが、忙しくしてじっくりと調べることが出来なかったことを、自分の「手持ちの本」をもとに、ネットで調べてみてもいいのではないでしょうか。 ただし、ネットだけで調べると、今までの日常と変わらないので、「手持ちの本」の内容をもとにすると、時間の使い方が変わりますね! |
|
| 仕事を部下の教材として意識! | ||
| 2020年 3月10日 (火) |
組織運営で、上司が、仕事を教材として部下にどのように提供するか、あるいは、工夫改善の力がある部下に、どのような仕事を担当させるか、かなり厄介な問題なのでしょう。 実力主義の社会では、目先の成績を上げることになりがちのため、中長期で考えることが難しいですね。 これは日本を代表する国会を見ていても、野党の質問は、政治に携わる人達を“育てる”という視点はまったくなく、目先のことだけにとらわれていますね! |
|
| 予期せぬ事態が発生すると! | ||
| 2019年 12月27日 (金) |
言葉による知識教育を受けていると、考えることが「知識優先」になってしまします。 「“五感”から得られる事実に基づく思考」をしなくなってしまいます。 知識で思考したほうが圧倒的に楽なためでしょう。 行き過ぎてしまうと、五感からの情報の取り方さえ出来なくなってしまうようです! |
|
| 大将的な性格のリーダーは! | ||
| 2019年 12月15日 (日) |
豊臣秀吉のように「人たらし」の人は、組織を「しくみ」で動かすことが苦手です。 これは、現代でも同じですね。 大きな成功をしても、その立役者がいなくなると、じわじわと力を失っていきます。 「人たらし」という単語の意味は、「他人を騙す人」という意味が正式だそうです。 騙しはやはり一時的な成功(?)でしかないのですね! |
|
| 「あなたなら大丈夫」とプラスの方向で! | ||
| 2019年 12月3日 (火) |
「悩んでいるとき」、「落ち込んでいるとき」などは、まず聞き役に徹することでしょうか。 そして、一段落してから「○○さんなら大丈夫ですよ」と声をかけるのでしょう。 「ああせよ」、「こうせよ」というのは、良いことはないのでしょう。 これは、子どもに対しても同じなのでしょう。 アドバイスは必要なことでしょうが、押しつけは良いことはないのでしょう! |
|
| 都合の悪い情報が推理力を鍛える! | ||
| 2019年 11月15日 (金) |
報告するとき(報告を受けるとき)、「良い・悪い」という判断をすることは、報告者(非報告者)の都合です。 組織として、「事実に基づいて判断する」という基本が、出来ていないのでしょう。 上司の顔色を見て動く組織になっているのでしょう。 これは、変化の少ない時代、大組織においては、都合の良いこともあったのでしょう! |
|
| 議論のとき、相手の逃げ道を! | ||
| 2019年 11月5日 (火) |
「自分が正しい」と思っているときほど、聞き役に徹することが大切なようです。 もちろん、「笑い」を引き出すことが出来れば最高ですが、それは難しいので、せめて、聞き役に徹することを目指したいですね。 別の手法としては、カードを利用する方法がありますね。 いろいろな意見をカードに記入し、似通ったもの、関連がありそうなものをグループ化し、整理する方法も有効ですね! |
|
| 組織はたえず異化作用が必須! | ||
| 2019年 11月3日 (日) |
いまは、社会の変化、あるいは、自然の変化が激しくなってきています。 絶えず異化(差異の著しい二つの性質を接近させるとき、両者の差異がさらにきわだつこと)作用をすることで、明日を見据えた変化を受け入れることが必要ですね。 そのためには、同質化をさけ、個性を尊重することが必要です。 学校教育も転換する必要が迫っているのでしょう! |
|
| 重要な意志決定は午前九時から十一時に! | ||
| 2019年 8月19日 (月) |
「決めごと」は、午前9時~11時までに行うこと、とのこと。統計的な分析結果なのでしょう。 ただ、ここでいう「決めごと」は、思考的なものごとに対する決めごとであり、五感を通じた情報に基づく「決めごと」は、対象ではないのでしょう。 五感による情報は、その都度決めなくてはならないものが、ほとんどですから。 なぜ違いがあるのでしょうか? |
|
| 弱さを人間関係の武器に! | ||
| 2019年 7月21日 (日) |
「弱さを武器」にされると対応が厄介ですね。 ただ、昨今の、社会への適応が苦手な人達は、弱さを武器にすることができず、自己否定、あるいは、社会否定になってしまうようです。 これは、もっと厄介ですね。ネット社会になり、自分の都合の良い情報のみ集め、その情報をもとに、自分の論理を組み立て、厄介な事件を起こす人も出てきてしまいます。 真夜中、人に見られないようにして、5寸釘でわら人形を立木に打ち込み、憂さ晴らしをしていた時代の方が、よかったのでしょうか? |
|
| 「なるほど、そうだね」と言おう! | ||
| 2019年 7月11日 (木) |
組織内で、あるいは、同じ業界内で、偉くなっていくと、多くの人は「思い込み」が、どんどん強くなっていくようです。 いろいろな人達の意見を、「なるほど、そうだね」と聞くことができる人は、「思い込み」が少ないのでしょう! |
|
| 人は感謝をされると幸せな気持ちになる! | ||
| 2019年 6月15日 (土) |
「感謝する」という行為が、お互いの「生き残りに有効だ」ということが、DNAに刻まれているのでしょう。 ネアンデルタール人は、体力や思考能力がホモサピエンスより優れていたのでしょう。 しかし、環境異変に遭遇したとき、お互いに協力し、感謝するということのDNAスイッチが、ONにならなかったため、亡びてしまったのでしょうか? いろいろな組織においても、長く長く生き残っている組織は、感謝DNAスイッチがONになっているのでしょう! |
|
| 成功した人は期待以上の奉仕をする! | ||
| 2019年 5月26日 (日) |
「奉仕(私心をすてて社会や他人のために働くこと)」が、風土として残っている地域があります。 四国八十八箇所巡りのお遍路での「お接待」も奉仕でしょう。 このお接待の見返りは、仏様から与えられる「何か=幸運」がある、ということでしょう。 「奉仕」といったものが、風土として定着しているところでは、ボランティアを「何らかの名誉といったものを得るために、やっているのでは?」といった雰囲気もあります! |
|
| 「叱る」という行為! | ||
| 2019年 5月12日 (日) |
現代は、五感ではなく言葉で他人と伝えることが多く、言葉に隠された“思い”はわかってもらえません。 そのため、「叱る」場合、その言葉だけで解釈されてしまいます。 表情や音色、視線、口元の表情などの変化で、“思い”を感じて貰うことは無理、と考えなければならないのでしょう。 いわゆる状況感受の受信能力が衰えているのでしょう。 ネット社会やAIが定着するほど、状況感受能力は衰えるのでしょうか? |
|
| 対人関係は、相手ではなく、自分を見直すこと! | ||
| 2019年 4月26日 (金) |
江戸時代は、地位=権力、名声=名誉、お金=禄高が、集中しないように、権力は老中にあるが禄高は数万石まで、名誉は学術的なものもあるが、公家が名誉を担っていたのでしょう。 この力の分散が、争いが起きなかった要因なのでしょう。 現在は天皇が名誉の面で大きな力を発揮でき、ひつとのところに力が集中しない仕組みになっているのでしょう。 もうすぐ「令和」の時代になりますね! |
|
| 自利を選んだ結果、犯罪を犯してしまう! | ||
| 2019年 4月22日 (月) |
2005年4月25日に尼崎市で起きたJR福知山線の脱線事故、直接的な犠牲者は死者107名(運転手含む)、負傷者562名でした。 この事故の原因は、手前の駅でオーバーランし、その遅れを取り戻すため、運転手がスピードを出し過ぎたためでした。 刑法的な見解では「運転手に罪がある」ということになります。 しかし、その背景には「時刻を守れなかった運転手には、厳しい再教育と待遇があった」ということです。 エリート達の「知性」と「理性」が造った“しくみ”が、最大の主因だったのでしょう。 現在の裁判では、裁けない問題ですね! |
|
| 自分の仕事をしていればいい? | ||
| 2019年 3月17日 (日) |
職場仲間で、会社が終わると飲みに行くことが無くなった今、職場内で声かけをしていかないと、チームとしての力が発揮できない。 かっては、トヨタ方式の「小集団活動」が盛んに行われていた時代は、飲み会がなくても、チーム力が十分発揮できていたのでしょうが、昨今は、それもそれほど活発でないところも多い。 相談や雑談などが少なくなると、発想力も弱くなり、固定観念が強くなり、個人主義も強くなるのでしょう! |
|
| 退職する人に、気持ちを込めて別れの挨拶! | ||
| 2019年 1月28日 (月) |
ここ数十年の核家族化で、子供時代に人との接し方を学ぶチャンスが、思っている以上に減少しています。 先生を除くと、両親の2人の大人と、お母さんの友人が1~2人、その人達を入れても3~4人との接触くらいです。 都会では近所づきあいもあまりないので、子供時代は人類史上初めての、少人数の大人達の中で成長していきます。 大人になって、いろいろな人々の中で、過ごしていくためのノウハウを身につけていないので、かなりきびしい生活になる人達がでてくるのでしょう! |
|
| 見当外れなプライド、メンツは頭の老化! | ||
| 2019年 1月24日 (木) |
こだわりが強くなっていくと、事実より、思い込みが上をいくことがあります。 そして、その思い込みを基準に判断するようになります。 昨年よく使われた「忖度」も、思い込みが支配しているのでしょう。 似たような現象に「地位の名称(社長、部長、むかしでは官位など)」があります。 これは権力争いにも利用されていたようです。 朝廷が、源義経に官位を与え、他の関東の武士に「ねたみ」を持たすような政策を行い、武士の勢力の分裂を図ろうとした例があります。 このような例はいつの時代にもあるのでしょう! |
|
| 人間重視それとも組織重視! | ||
| 2018年 12月29日 (土) |
成長期には組織重視、低迷期は人間重視が社会の基本です。 現在のようにそれほど成長が期待できないときは、人間重視です。 具体的には「笑顔重視」なのでしょう。 アメリカのように対立し、笑顔が少なくなりそうな社会では、混乱が拡大するのでしょうか! |
|
| 空気を読むか、読まないか! | ||
| 2018年 12月7日 (金) |
社風があるのと同じように、日本の各地にも風土というものがあります。 たとえば、瀬戸内海沿岸は大阪の風土に馴染みやすい。 山陰や北陸は京都の風土に馴染みやすい。 東北は東京なのでしょうか。 関西はそれぞれの地域に、それぞれの風土がありますが、関東は比較的似通っています。 自分の育った風土と社風とがうまく合うと、気持を楽にして働けるのでしょう! |
|
| 一生懸命に上司に仕えてきた人! | ||
| 2018年 12月1日 (土) |
“見下す”ことが定着した人は、年齢にかかわらず、その意識を解除することが難しい。 それでなくとも、長い期間、特定の組織、あるいは業界に属してしまうと、特定の考え方が染みこんでしまい、その思考から抜け出せなくなってしまいます。 いわゆる「脳の老化」です。 ある程度の年齢になると、「広く、浅く」知識を広めていくことが、脳の老化を防ぐことにつながるのでしょう! |
|
| 信望を寄せてくれるマネジャー! | ||
| 2018年 10月28日 (日) |
パワハラ問題が注目されています。同じようなことを行っても、パワハラとは受け取られないこともあります。 上司あるいは指導者が、自分の思い込みや自己満足で指導してしまうと、パワハラとして受け取られるようです。 相手(指導される側)が、自分のために一生懸命に指導してくれている、と感じると、名指導者・名コーチとして評価されます。 指導する側が、自分を捨て、事実(現在の状況)のみに目を向けることが、出来るかどうかですね! |
|
| トップを目指すのならば! | ||
| 2018年 5月9日 (水) |
「忖度」という言葉が定着してきました。 しかし、大昔より組織内での出世を目指すなら、上司の顔を見て、ご機嫌伺いをしながら仕事をすることが常識。 官庁の人事を、2014年より官邸主導で行うようになり、より大臣などの顔色を伺う必要性が高まった結果、「忖度」が定着したのでしょう。 いまの国会での野党の政府追及は、法律を整備する国会議員の役割から言うと、制度・システムの不具合を追求すべきなのでしょう! |
|
| でも、あるときから人のためだけに! | ||
| 2018年 4月30日 (月) |
「仕事」という概念を、変えなければいけない時代が近づいているようです。 AIが進歩し、ロボットが人間の多くの仕事を肩代わりすると、「仕事」という概念はどのように変化するのでしょうか? 団塊の世代は、人間史上もっとも変化に対応してきた人達です。 その最後の変化がAIロボット時代なのでしょう。 変化を起こす側にはなれないのでしょうが、見届けることはできるのでしょう! |
|
| いい仕事をしている人の“美学”! | ||
| 2018年 4月24日 (火) |
現在の国会を見ていると、野党議員の質問にがっかりする。 議員1人当たりの国費は年1億円程度。そのお金が「文書改変の追求」や「忖度の有無の追求」に使われるのはもったいない。 その役目をする組織を作れば、たとえ一人に一千万円かかったとしても、大幅に経費節減になる。 参議院を廃止し、官庁の監査機関を改変強化したほうが、はるかに少ない費用で成果が期待できる、と主張する人たちがいても、少しも疑問はない! |
|
| 逃げ方の代表「どうしましょうか?」 | ||
| 2018年 3月20日 (火) |
人類が、伝達の手段として「言葉」というものを使い出したのは、ハッキリとは分からないようですが数千年前ではないかと言われています。 人類の歴史から考えると、つい最近ということになります。 伝達の方法として、顔の表情、視線、手足の動き、それとイラスト等々で伝達していたのでしょう。 最古の土器である縄文土器は、形が複雑です。なにかを伝えていたのでしょか? |
|
| 強い立場を利用して! | ||
| 2018年 3月14日 (水) |
女子レスリング界でパワハラが問題になっています。 やっている側はそれほど意識していないようです。 上司と部下という関係ではないのですが、野党の国会議員の発言は、一般社会ではパワハラ発言になるのでしょう。 お偉い議員が過激な発言を繰り返しているので、一般社会でも「あの程度ならOKなのだ」と思われてしまいますね! |
|
| とっておきのマナー「笑顔」! | ||
| 2018年 3月10日 (土) |
「笑顔」は言葉がまだない時代から、人と人をつなぐ重要な手段だったのでしょう。 言葉が発達しはじめたのは、おそらく数千年前、それまでの50万年間に、表情、ジュスチャアー、絵と徐々にコミュニケーション術を開発してきたのでしょう。 「笑顔」はどのくらい前から使われるようになったのでしょうか! |
|
| 上司から言われた通りに! | ||
| 2018年 1月27日 (土) |
組織に於いて「言われたとおりにやれ」とか、「マニュアル通りにやれ」という組織があります。 マニュアルを作っていた時代の人達は、マニュアルの背景についても経験がありました。 しかし、マニュアルで育った人達は、経験が乏しいのです。電車が時々止まる、あるいは、大きな工場で事故が起きています。 体験が少なくなっているのでしょう。 むかしは「ワザは盗め」といった時代でした。 マニュアルを見て一人前になったとする時代は、そろそろ見直しが必要ですね! |
|
| 一人相撲ではみんなの力を引き出せない! | ||
| 2018年 1月10日 (水3 |
貴乃花親方は、「一人相撲」がお好きなようですね。そうであるのなら、相撲協会を脱出し、神々が住んでおられる山々に行って、一人相撲をとるのでしょうか? 瀬戸内海の大三島にある大山祇神社は、山の神・海の神・戦いの神として歴代の朝廷や武将から尊崇を集めた。 大山積神を祀る代表的な神社。大祭には目に見えない稲の精霊と相撲をとる一人角力(ひとりずもう)が奉納されています! |
|