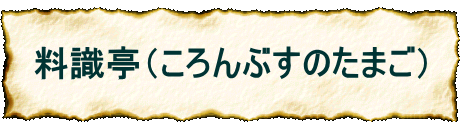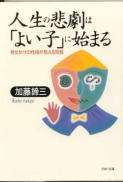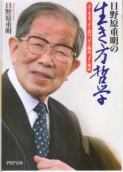現代は、「ストレスから解放される時間」が少なくなっています。
その最大の原因は、「歩かなくなった」ことでしょう。
「歩き方」を学び、「歩く効果」を学ぶことが必要なのでしょう。
小学校で「歩き方を教わった」経験がありますか?
「遠足」の前に、歩き方を教わっていますか?
その土地に関する歴史、言い伝え、民話、伝説などを教わって、遠足に行っていますか?
その最大の原因は、「歩かなくなった」ことでしょう。
「歩き方」を学び、「歩く効果」を学ぶことが必要なのでしょう。
小学校で「歩き方を教わった」経験がありますか?
「遠足」の前に、歩き方を教わっていますか?
その土地に関する歴史、言い伝え、民話、伝説などを教わって、遠足に行っていますか?
か05-10
加藤諦三
この本は親子の問題を論じているが、同時に、それを通して自分の潜在的な可能性をどう実現するかを考えたものである。自分が幼い頃に受けた心の傷を無視して生きようとすれば、必ず生きることへの無意味感や、劣等感に悩まされる。心の傷に生涯支配されてしまうのだ。私もその一人であるが、小さい頃「よい子」であることが幸福の条件であると思い込んで、自分の本性を裏切り続けてきた人がいる。そこで、そういう人のために、人間にとって最善の生き方とはどのようなものか考えていきたいと思う。
か67-01
香山リカ
職場において心の病で休職する人たちが増えている。その年齢層は、三〇代が約六割。彼らの特徴は、学齢は高く、まじめだが、やや自己中心的。そして、仕事以外の趣味には精力的で、休職中に海外旅行に出かける人もいるという。この症状は、果たして病気なのか? 本書では、時代の空気を鋭く読み解くことで定評の精神科医が、急増中の「新型うつ」を分析する。『仕事中だけ「うつ病」になる人たち』を改題。
ひ08-03
日野原重明
人間は老いと死に向かって歩いていく。その不安の中でも、できるだけ老化を抑制するよう自らも努力し、医師にも手伝ってもらう。そして、死に向かって生きる歩みの中に生き方を考え、「ありたい自分の姿」を発見するという生き方をしたい、と著者は提唱する。半世紀以上、内科医として人の命に寄り添ってきた94歳の現役医師のメッセージは、最後の一瞬まで、志高く、元気で生きるための実践哲学だ。