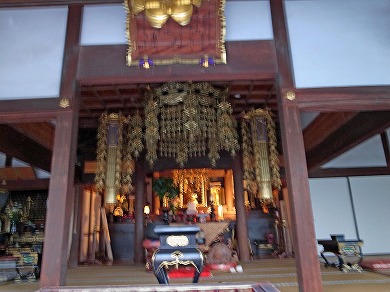江戸時代に寺子屋が隆盛し、その結果、十八世紀の日本人の識字率は、フランス人やイギリス人よりも上で、世界一だったともいわれています。
これは参勤交代によって、江戸の文化が全国に広がった影響があるでしょう。そして各地に寺子屋や私塾、藩校などが存在し、子どもたちの多くが
読み書きを学んでいたのです。
寺子屋の中には「二律背反」ということを教育のコンセプトとしています。片方に偏らず、両方のバランスを考えるのです。教育には、厳しさが必要でが、自由も必要です。片方に偏らず、両方のバランスを考えたのです。
また、寺子屋は、先生と生徒が決まっていませんでした。生徒の中の上級生が後輩に教えるという形だったそうです。